東証一部上場企業のソニーフィナンシャルホールディングス(SFH)が上場廃止し、ソニーの完全子会社となる。40年ほど前、米生保との合弁事業から始まり、売却検討、上場と進んできたソニーの金融事業が、ようやく落ち着くべきところに落ち着いた。(文=関慎夫)
ソニーの経営と金融事業の位置づけ
金融事業持ち株会社がソニーの完全子会社に
東証一部上場企業のソニーフィナンシャルホールディングス(SFH)。社名を見ればわかるとおりソニーグループの一員で、傘下にソニー生命保険、ソニー損害保険、ソニー銀行等を持つ中間持ち株会社だ。
8月31日、SFHは上場廃止となる。これまでソニーの持ち株比率は65%だったが、7月にソニーによるTOBが成立、9月2日をもってソニーの完全子会社となるためだ。
ソニーグループでは、以前、国内音楽部門を担当するソニー・ミュージックエンタテインメントも上場していたが、2000年にソニーの完全子会社となった。SFHの上場廃止でソニーグループにはソニー以外の上場会社はなくなり、持ち株会社であるソニーが、すべての事業を完全掌握することになる。
ハードとソフトの両輪経営
ソニーが「ハードとソフトの両輪経営」であることはよく知られるところだ。
映画・音楽を自らの機材を使って制作し、そのコンテンツをソニー製品によって視聴する。電機業界ではかつてパナソニックや東芝、パイオニアなども映画会社を買収・出資しハードとソフトの融合を標榜したこともあるが、いずれも撤退し、今ではソニーだけが世界で唯一無二の両輪経営企業となっている。
プレイステーションによってゲーム事業に参入できたのも、ハードビジネスとコンテンツビジネスそれぞれに人材が揃っていたためだ。
ちなみにソニー前社長の平井一夫は、ソニー・ミュージックに入社し、ゲーム事業のソニー・コンピュータエンタテインメント(現ソニー・インタラクティブエンタテインメント)社長を務め、最後はソニー社長となったのだから、まさに「両輪経営」の体現者と言っていい。
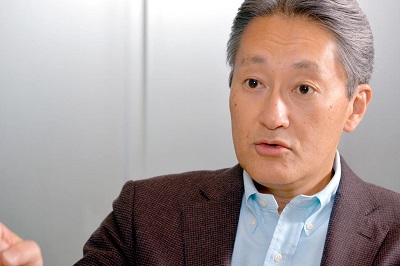
金融はハード、ソフトと並ぶ中核事業
電機メーカーとして1946年に誕生したソニーは、ソフト部門に進出したことで、事業領域を一気に拡大した。では金融部門に持つようになったのはなぜか。
昨今、インターネット企業が金融部門を持つのは半ば常識になっている。またイオンやセブン&アイなど、消費者と接点の多い流通業も金融子会社を持っている。
メーカー系でも、トヨタ自動車など豊富な内部留保を元に金融収支で大きな利益を上げている会社もある。しかしトヨタにとって金融事業はあくまで自動車販売のサポートという位置づけだ。ところがソニーは違う。
「金融事業は、エレクトロニクス、エンタテインメントとならぶコア事業であり、長期視点で成長領域と位置 付けている」
と吉田憲一郎・ソニー社長が言うように、ソニーにとって金融事業はハードとソフトと並ぶ中核事業という位置づけだ。
収益面からもそれは明らかだ。ソニーには、エレキ、半導体、映画、音楽、ゲーム、金融の6事業部門があるが、先日発表した第1四半期のセグメント別営業利益を見ると、金融部門は472億円とゲーム部門1240億円に次ぎ2番目に収益に貢献している。
ソニーの金融事業の歴史
銀行を持ちたかった創業者・盛田昭夫
ソニーの金融部門は、1979年に米プルデンシャルとの合弁でソニー・プルデンシャル生命保険」が誕生したことに端を発する(営業開始は81年)。日本進出を狙っていたプルデンシャルに対し、ソニー創業者の1人である盛田昭夫が「うちと組まないか」と持ち掛けたのがすべての始まりだった。
盛田の本音は「銀行を持ちたい」だった。来年、ソニーは創業75周年を迎えるが、その前半は資金調達の苦労が絶えなかった。
創業期のソニーは、創業者で天才発明家の井深大のアイデアを形にするため、盛田が資金調達と営業を担当していた。井深の書いた設立趣意書に「他社の追随を絶対許さざる境地に独自なる製品化を行う」とあるように、ソニーは創業時から今まで市場に存在しない独自製品の開発を目指してきた。
当然、新製品の開発にはお金がかかる。当初は愛知県で造り酒屋を営む盛田の実家が支援していたが、規模が大きくなるにつけそれでは追いつかなくなる。今と違ってベンチャー企業に資金を提供するVCは存在せず、銀行は実績の乏しい会社への融資には慎重だ。ソニーは常に資金不足に悩まされていた。
58年に東証上場するが3年後には日本企業として初めてADR(米預託証書)による資金調達に成功、70年にはやはり日本企業初のニューヨーク証券取引所に上場を果たしたのも、すべて旺盛な資金需要を満たすためだった。

生命保険から金融事業に参入
そうした苦労を重ねることで、盛田の「銀行を持ちたい」との夢は大きくなっていく。「グループ内に銀行があれば資金調達も簡単にできる」との狙いであり、実際、検討も始めていた。
しかし90年代に日本版ビッグバンが導入されるまでは、銀行への新規参入は事実上閉ざされていた。そこで盛田は、プルデンシャル会長の話に飛びついたのだ。
前述のように、人真似をしないのがソニーのDNAだ。ソニー・プルデンシャルも同様に、日本で初めてライフプランナー(LP)を採用した。それまでの生保業界は、「生保のおばちゃん」が足繁く顧客のもとに通い、契約を取るというのが一般的だった。
ところがソニー・プルデンシャルは、経済や金融の知識を持つLPが顧客のライフプランを提案する提案型営業で契約を伸ばしていき、「カタカナ生保」の中では断トツの実績を残した。
その後、プルデンシャルとの提携を解消し、ソニー生命へと社名変更したのが91年、96年にはソニーの100%子会社となる。
ソニーのエレキ事業は景気や為替の影響を受けやすい。一方、エンタメ事業は水物で、特に映画は大当たりもあれば大ゴケすることもある。その点、ソニー生命はコンスタントに利益を上げ、ソニーの経営を下支えし続けた。
出井会長の求心力を削いだソニー生命の売却案
ところが2002年、ソニー生命に激震が走る。当時会長の出井伸之が突然「ソニー生命を売却する」方針を示したのだ。
理由はソニー生命が成長した結果、その資産が貸借対照表の2割を占めるまでになり、出井はこれを過度な依存でありリスクと考えた。さらには対面販売の生保は、インターネット時代にそぐわないとの判断もあった。
しかしこれに対してソニー生命社員だけでなく、グループの役員・社員の大半が反対した。「自ら市場を開拓したソニー・スピリッツの体現者を無碍に扱うとは何事だ」というわけだ。
さらには契約者からも反対の声が出て、結局、売却話は白紙となる。この翌年にはソニー・ショックが起きるのだが、こうした一連の出来事で出井の求心力は急速に失われていき、05年の退任へとつながる。

強まる金融事業切り離しへの圧力
ソニー生保から遅れること19年、ソニー損保が1998年に誕生(営業開始は翌年)。2001年にはソニー銀行が設立された。そして04年、中間持ち株会社SFHを設立、ソニー生命、ソニー損保、ソニー銀行の3社がぶら下がる形となる。
さらに07年、SFHは上場する。この時調達した金額は、ソニー、SFH合わせて約3500億円に達した。
SFH上場の翌年、リーマンショックが起き、これをきっかけにソニーは深刻な業績不振に陥る。そこでテレビ事業の別会社化やパソコン事業などの構造改革に取り組んでいくが、SFHの上場益が財務面では大いに役に立ったことは言うまでもない。
しかし親子上場はいいことばかりではない。ソニー、SFHはそれぞれ別の株主が存在するため、利益相反になる可能性もある。意思決定のスピードも遅くならざるを得ない。実際、アクティビストの米サード・ポイントはソニーに対して金融事業の切り離しを求めていた。
ソニーの金融事業の着地点
こうした声に応えたのが、今回の完全子会社化だ。
「上場子会社という一定の制約のもとに独自の資金調達手段を保持するよりも、迅速かつ柔軟な経営判断を優先し、経営の選択肢を広げ、グループシナジーを追求する」(吉田社長)
ソニーは現在、継続的に収入を得るリカーリングビジネスに力を入れている。金融機関を持つことは、その上でも有利に働く可能性がある。そうなれば吉田社長の言うグループシナジーが現実のものとなる。
100%子会社化するためのTOBに、ソニーは約4000億円を投じた。13年前に上場で得た資金より約500億円高い数字だ。
ただし、その結果として「今後、連結ベースで年間400億~500億円程度の純利益の増加を期待できる」(十時裕樹副社長兼CFO)という。これまで株式配当の35%が外部に流出していたが、今後は100%、ソニーに入ってくるためだ。
また、エレキや半導体、映画、音楽などと並んでソニー本体にぶら下がるということは、他の事業と同格となることだ。それが吉田社長の言った「コアビジネス」の真意である。




