コロナ禍で巣ごもり需要が増したこともあり、アマゾンの日本での事業が急拡大、売上高は2兆円を超えた。日本国内での売り上げを公表するようになってから8年で3倍となったが、その勢いは衰える気配を見せない。リアル小売業はいかに対抗していくのか。文=ジャーナリスト/下田健司(『経済界』2021年10月号より加筆・転載)
「兆超え」はアマゾン、楽天、Zホールディングス
国内小売業界で米アマゾン・ドット・コムの勢いが加速している。2020年の日本国内売上高は2兆円を超えており、8年で3倍超に拡大した。
アマゾンが公表した2020年12月期の年次報告書によると、日本事業の売上高は前期比27・9%増の204億ドル。年平均為替レート1ドル=107円換算で2兆1893億円(25・5%増)となり、初めて2兆円を超えた。20年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出自粛が広がり、いわゆる巣ごもり需要が高まったことが追い風となった。
この2兆円という売り上げ規模は国内小売業界でトップクラス。流通大手2社の21年2月期の売上高を見ると、トップのイオンが8兆6039億円、2位のセブン&アイ・ホールディングスが5兆7667億円。小売り大手2社に次ぐ業界3位につけている。
国内ネット企業のEC(電子商取引)規模はどれくらいか。大手の楽天グループと、ヤフーを傘下に持つZホールディングスを見てみよう。
楽天の20年12月期の国内EC流通総額(取扱高)は19・9%増の4兆4510億円だ。国内EC流通総額には、楽天市場をはじめ、トラベル、ブックス、ゴルフ、ファッション、ドリームビジネス、ビューティ、デリバリー、楽天24、オートビジネス、ラクマ、楽天西友ネットスーパーなどが含まれる。このうち楽天市場の流通総額は3兆円を突破している。
一方、Zホールディングスの21年3月期のEC関連サービス全体の流通総額は24・4%増の3兆2268億円だった。このうち、ヤフーショッピング、PayPayモールなどのショッピング事業(ECモール)の取扱高は同45・1%増の1兆5014億円だった。
アマゾンの日本事業の売上高には、オンラインストア(直販)、マーケットプレイスの手数料収入、サブスクリプションサービス、クラウドサービスのAWS(アマゾン・ウェブ・サービス)などが含まれる。アマゾンは流通総額を公表していないが、3兆円を超えると見られている。
楽天が流通総額4・5兆円で頭一つ抜けている格好だが、アマゾンは国内EC業界においても強大な存在感を示している。
アマゾンの日本でのこれまでの事業展開を振り返っておこう。アマゾンが日本に進出したのは2000年。千葉県市川市に物流センターを構え、日本語サイトを開設。和書洋書約170万タイトルの販売からスタートし、CD・DVD・ビデオ・ソフトウエア・ゲームなど取扱商品を拡大していった。取扱商品はその後、日用品、家電、玩具、スポーツ、衣料品、食品、文具など矢継ぎ早に拡張。並行して物流センターを主要消費地に開設していった。
02年には第三者間で商品を売買するプラットフォーム「Amazonマーケットプレイス」を導入。07年には、会員制プログラム「Amazonプライム」を導入した(現在、年会費4900円で、配送料無料、動画視聴無料、聴き放題や読み放題などの特典がある)。
17年には、生鮮食品や日用品を最短で当日に配達するプライム会員向けサービス「Amazonフレッシュ」を開始。19年にはスーパー大手のライフコーポレーションと組んで、プライム会員向けにライフの生鮮食品や日用品を配達するサービスを開始している。今年6月からは、岐阜県を地盤とするスーパー大手のバローとも同様の協業を開始した。
取扱商品を拡張し、サービスを次々と投入していったアマゾンだが、日本事業の売上高が明らかになったのは13年のことだ。
アマゾンは12年12月期の年次報告書で日本事業の売上高を初めて公表した。その額78億ドル。12年の平均為替レート換算で6240億円。EC事業者として国内最大級で、小売業界でも大手の一角に迫る規模であることが判明し、EC業界や小売業界がざわついた。売上高が明らかになり、アマゾンの脅威が現実のものとなった。
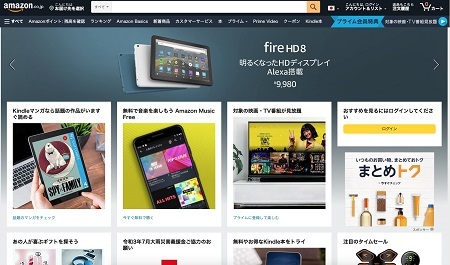
米国の小売業者にとってはアマゾン禍
大手の経営破綻が相次ぐ米国小売業界の動きも脅威を増幅していった。
この10年ほどを見ても、書店のボーダーズ(11年)、家電量販店のラジオシャック(15年)、玩具店のトイザラス(17年)、シアーズ・ホールディングス(18年)、アパレルのフォーエバー21(19年)、百貨店のニーマン・マーカスとJCペニー、アパレルのJクルー(20年)などが経営破綻している。
もともと経営不振に陥っていた企業も多く、すべての破綻要因がアマゾンの影響によるものではないが、多くはアマゾンの影響としてとらえられた。それもそのはずで、アマゾンの北米の売上高は10年に187億ドルだったのが20年には2362億ドルと約13倍に拡大している。
アマゾンは拡大の手を緩めない。17年にはスーパー大手のホールフーズ・マーケットを買収した。15年からは書店「アマゾン・ブックス」、18年からはレジ無しコンビニ「アマゾン・ゴー」を展開、20年にはレジ無しスーパー「アマゾン・ゴー・グロサリー」をオープンするなど、実店舗展開にも乗り出している。
こうした動きに対して、既存小売業は実店舗とオンラインの融合を図り巻き返しを図る。その急先鋒がウォルマートだ。対アマゾンの姿勢を明確に打ち出しデジタルを強化。18年には、実店舗を想起させる「ストアーズ」を社名から外し、EC部門を強化していった。
米国小売業界でのアマゾンの存在感は日本の比ではない。業界団体の全米小売業協会の20年米国内売上高ランキングによると、アマゾンの売上高は1872億ドル。4308億ドルでトップのウォルマートに次いで2位につける。ちなみに、米報道では22年にも流通総額でアマゾンがウォルマートを上回るとの金融機関の予測を伝えており(両社は流通総額を公表していない)、流通業界におけるアマゾンの支配力は一段と高まっている。
日本の2大小売業、イオンと7&Iのアマゾン対抗策
日本でも、アマゾンの攻勢に対して、小売り大手2社はデジタル強化を打ち出している。
イオンは25年を最終年度とする中期経営計画の中で、26年2月期のデジタル売上高を1兆円(20年2月期は700億円)に引き上げる目標を掲げた。
25年にデジタル売上高1兆円を目指すために、既存のネットスーパー、ECを伸ばし顧客基盤を拡大。併せて、英ネットスーパーのオカド社との提携によりAI(人工知能)を活用した自動倉庫を23年に稼働、次世代型ネットスーパーをスタートさせ売り上げ拡大を図る。これにより「オンラインデリバリー=イオン」というイメージをつくり上げる狙いだ。
イオンは過去の中期経営計画の中でもデジタル強化を掲げ、さまざまな手を打ってきたが、今のところデジタル売上比率は1%にも満たないだけに、目玉事業のオカド社との提携による次世代型ネットスーパーでどこまで結果を出せるかがポイントになっている。
一方、セブン&アイの25年度を最終年度とする中期経営計画での重点戦略の一つがデリバリーサービスだ。とくに、セブン-イレブンが手掛ける「セブン-イレブン ネットコンビニ」の拡大を打ち出している。
ネットコンビニはセブン-イレブン店舗からの配達サービス。対象商品は店内商品の9割以上、約2800アイテム。スマートフォンで注文し、最寄りの店舗を指定すると、最短30分で届く。1千円(税別)以上の注文から受け付け、配送料は330円(税込)だ。17年に北海道でサービスを開始し、広島県、東京都に拡大。今年2月末時点で、約350店でサービスを導入している。
高密度に張り巡らされたセブンの店舗網やリアルタイム在庫管理などを生かしたサービスと言える。現在、セブンの商品だけでなく、グループ会社の商品配達もテスト中だ。21年度末までに1千店に増やし、25年度に全国展開を完了させる計画で、営業利益を5%押し上げる目標を掲げる。
セブン&アイもこれまでオンラインを強化してきたが、EC売り上げ規模はまだまだ小さい。ECではグループで最も売り上げ規模の大きいイトーヨーカ堂のネットスーパーの売り上げがここ数年減少傾向にある。グループのEC売上高も伸び悩み、21年2月期は1041億円だった。
経済産業省によると、20年の国内EC化率は前年の6・76%から8・08%に上昇した。新型コロナ感染症拡大のための外出自粛が追い風となったためだ。イオン、セブン&アイの大手2社のEC化率はこれに遠く及ばない。アマゾンをはじめとしたネット企業の攻勢が続くなか、成長戦略の要と位置付ける以上そろそろ結果を出すときに来ている。
