講談社、集英社、小学館の三大出版社ほか、バンダイナムコフィルムワークス、エイベックス・ピクチャーズなど日本を代表するIPホルダー13社が出資し、映像配信サービス向けのアニメ作品を供給するアニメタイムズ社。設立10周年を迎えたいま、世界進出を本格化する。(雑誌『経済界』2025年4月号より)
勝股英夫 アニメタイムズ社社長のプロフィール
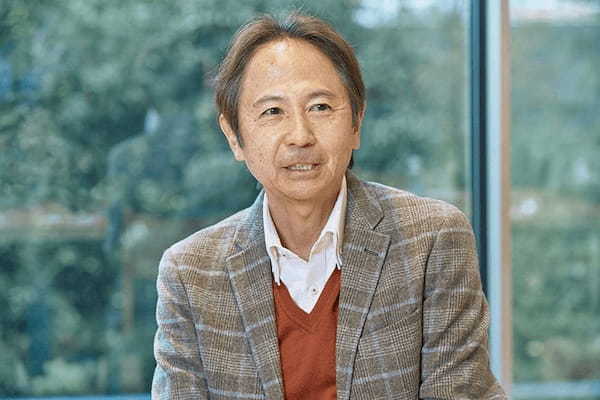
かつまた・ひでお 1988年ソニー入社。SPE・ビジュアルワークス(現アニプレックス)の設立メンバーとなり、アニプレックス専務、A-1 Pictures社長などを経て、2012年エイベックス・グループへ移籍。14年エイベックス・ピクチャーズを設立し取締役を務める。15年アニメタイムズ社を設立し社長に就任。17年よりエイベックス・ピクチャーズ社長を兼務する。
三大出版社を中心に外資と対等に向き合う
―― 2015年に会社を設立しました。
勝股 Netflixが日本上陸し、Amazonもプライム・ビデオをスタートした配信元年と言われる年でした。そんな黒船襲来という時代の到来に際して、アニメコンテンツにおいては、コンテンツホルダーが集合体として、大手外資プラットフォーマーと対等に向き合い、配信マーケット全体を成長させていく必要性がありました。
当時、アニメ配信サービスとしては、NTTドコモとKADOKAWAによるdアニメがスタートしていました。通信会社がメインになってプラットフォームなどインフラを整備し、そこにアニメをはじめ総合エンターテインメントコンテンツを載せる動きが出始めた頃です。そんななか、日本のコンテンツホルダーが主体になる、オールジャパンのアニメチャンネルを作ることを掲げて、講談社、集英社、小学館を中心にアニメスタジオが集まって動き出しました。
―― 競合同士でもある三大出版社が協業に動いたのには、大手外資の参入への危機感がそこまで大きかったということも背景にあるのでしょうか。
勝股 もともと3社の間では、海外事業などは協力し合う意識があったんです。共同で出資している事業もいくつかあります。加えて、市場が急速に出来上がっていく状況のなかで、相手が巨大な外資だけに、国内で対峙、乱立している場合ではありませんでした。もしいまだったら、それぞれ単独でやっているかもしれませんけど(笑)。
―― 3社のアニメ作品は、新作から旧作まですべてアニメタイムズで見られるのでしょうか。
勝股 新作はそれぞれ製作委員会の出資者がいるので、作品ごとの契約によって配信有無や配信時期が変わります。ただ、旧作はほとんど見られます。いまのアニメファンは、ひとつの作品を取っ掛かりに、監督やスタジオで掘り下げていきます。そのニーズに応えられるのが、われわれの強みのひとつです。
イン・プラットフォーム戦略。本格的な海外進出はこれから
―― 21年にAmazonプライム・ビデオに専門チャンネルを開設しました。
勝股 われわれは、アニメ作品のプログラムサプライヤーです。設立当初から、NTTドコモとエイベックスによるd TV(現・Lemino)やケーブルテレビなどの総合チャンネルに、アニメ番組を供給していました。現在でも、NetflixやDisney+のほか、いろいろなプラットフォームに作品単位で番組供給をしていますので、アニメタイムズの専門チャンネルを持ちながらも、全方位の番組供給も同時に行っています。
―― 独自の配信サービスのローンチも検討されましたか。
勝股 プラットフォームはとても重いインフラで、立ち上げて運用するには、大変な時間とコストが必要になります。なのでわれわれは、コンテンツホルダーの集合体をひとつのプラットフォームとする考え方「プラットフォーム・イン・プラットフォーム戦略」にシフト。それを形にしたのが、Amazonプライム・ビデオのアニメ専門チャンネル・アニメタイムズ開設です。今後もこの形態を拡大、拡充していくことを考えています。
―― 日本アニメは世界で人気です。海外進出戦略を教えてください。
勝股 Netflixなどグローバルプラットフォームへの供給からの世界配信のほか、23年12月からアニメタイムズ・チャンネルを海外のプラットフォームに置く施策を進めています。現在はインドのAmazonに開設していますが、まだ第一歩という段階です。これからアジアやアフリカ、中近東などグローバルサウスへの進出を考えています。一方、欧米でも十分可能性はある。そのあたりを順次、攻めていきます。
―― 競合として意識するチャンネルやプラットフォームはありますか。
勝股 アニメを配信しているサービスは、すべて競合と言えますが、一方で、ユーザーに、どこでもアニメを視聴できる環境を提供し、アニメファンを醸成していくという意味では、仲間ともいえるかと思います。われわれはいままで国内で事業をしてきて、ある程度の市場を得ています。これからは海外で新参者として戦っていきます。
―― 海外進出におけるアニメタイムズの優位性や差別化のポイントはどう考えますか。
勝股 出資者が日本を代表する13社のコンテンツホルダーであり、そのバックアップを受けていることがいちばんの強みですね。アニメ作品のカテゴリーで言うと、ファミリー層向けの王道アニメから、いわゆるコア層向けのシーンアニメまで幅広く取り揃えています。特にファミリー層をターゲットにできる編成が、膨大なコンテンツを持つわれわれならではの特徴です。
コンテンツホルダーに対し、10年間で200億円を還元

―― 設立から10年の軌跡をどう振り返りますか。
勝股 外資のグローバルプラットフォーマーやメディアなどとは異なるスタンスで、コンテンツホルダーに寄り添いながら、一緒に歩んできた10年だったと思います。この間に権利元に還元してきた総額は200億円に上ります。持続的な継続のなかで、業界に貢献してきた自負はあります。
―― 業績の成長への転機はありましたか。
勝股 やはり21年のアニメタイムズとしての専門チャンネルの開設ですね。ブランディングのための宣伝や調達に注力し、国内での大きな実績につながりました。このモデルを現在海外で展開しようとしています。
―― Netflixは一時期、国内の有力アニメスタジオと提携してオリジナル作品の制作に力を入れていました。その動きをどう見ていましたか。
勝股 その結果が、『鬼滅の刃』をはじめ、ほかプラットフォームと横並びのテレビアニメ作品を多く配信し、それが視聴ランキングの上位を占める現在です。確かにそこでしか見られないコンテンツは重要ですが、世界的にヒットするかは、時代の流れや時の運によります。当時、オリジナルがひとつでも世の中的なヒットになっていれば、状況は違っていたかもしれません。
一方、Netflixは実写ではヒットを連発していて、ローカルオリジナルで成功しています。アニメに関しては、いまは『週刊少年ジャンプ』の漫画原作などメジャーに向いていますが、またいずれオリジナルに回帰する流れが来るでしょう。
アニメと音楽の相乗効果で価値が上がる日本エンタメ
―― 会社としての現在の課題は。
勝股 やはり海外進出の対応ですね。海外でチャンネルを開設するためには、膨大な数の作品の字幕や吹替え制作といったローカライズが必須になります。特に子ども向け作品は吹替えを入れなくてはならず、すべてローカライズすると、インドのケースでは22言語の対応が必要になります。ヒンズー語圏内で4億人、いちばん少ない22言語目でも400万人の市場になりますので。
一方、スピードも求められます。日本で新作が発表されると、ファンサブというファンが字幕を入れる海賊版などがすぐ出回るので、そういう違法海賊版への対策としても、ローカライズはコストとスピードの両方で最重要課題のひとつになります。
―― それでも海外はやっていかないといけない市場ですね。
勝股 日本アニメは特に海外ユーザーからの引きが強く、欧米でもアジアでも潜在的なポテンシャルは高い。ハリウッドIPと比較されるほどの存在になっていますので、出せば響くのですが、まだほとんど届けられていないのが現状です。
この先、スピードを追求するケースでは、生成AIによる字幕も導入されるかもしれません。100%の確度でなくても、まず出して、メンテナンスしていけばいい。そこが配信のメリットです。いまは声優さんのいろいろな問題がありますが、吹替えもいずれローカライズは生成AIなどの技術をどんどん検討していく段階になると思います。
―― 日本アニメの世界進出では、主題歌など音楽にもリンクして同時にヒットします。韓国のコンテンツ輸出とは形態が異なると感じます。
勝股 日本コンテンツは、アニメやゲーム、音楽などの要素がバリューチェーンとして一体になったときに、世界的に価値が上がるという言い方もできます。単体で打って出て成立している他の国との違いは、そういう各要素が連動したときの日本の総合的なエンターテインメントの強さであり、強みです。そこは意識したほうがいいかもしれませんね。
―― 今年は10周年の節目の年です。
勝股 この10年、赤字を一度も出していない会社であり、ここ数年はまた大きく伸びるフェーズに入っています。23年8月よりECサイト「アニメタイムズSTORE」を世界114の国と地域で本格稼働していますが、人気アニメパッケージやグッズにとどまらず、2・5次元舞台グッズや声優コラボ商品、イベント限定グッズなども取り扱い、売上は右肩上がりで伸びています。10周年を機に、これまで国内中心だった事業を、より海外に向けて打って出たいと考えています。
