短期間での英語力向上にコミットするプログリット。創業者の岡田祥吾氏は、大学卒業後、起業を目的にコンサル会社のマッキンゼーに入社、そこで馬車馬のように働いた。当時、岡田氏は何を考えて働いていたのか。そしてその経験はプログリットにどのようにつながっているのか。聞き手=関 慎夫 Photo=横溝 敦(雑誌『経済界』2025年5月号「社長が語る入社1年目の教科書」特集より)
岡田祥吾 プログリット社長のプロフィール
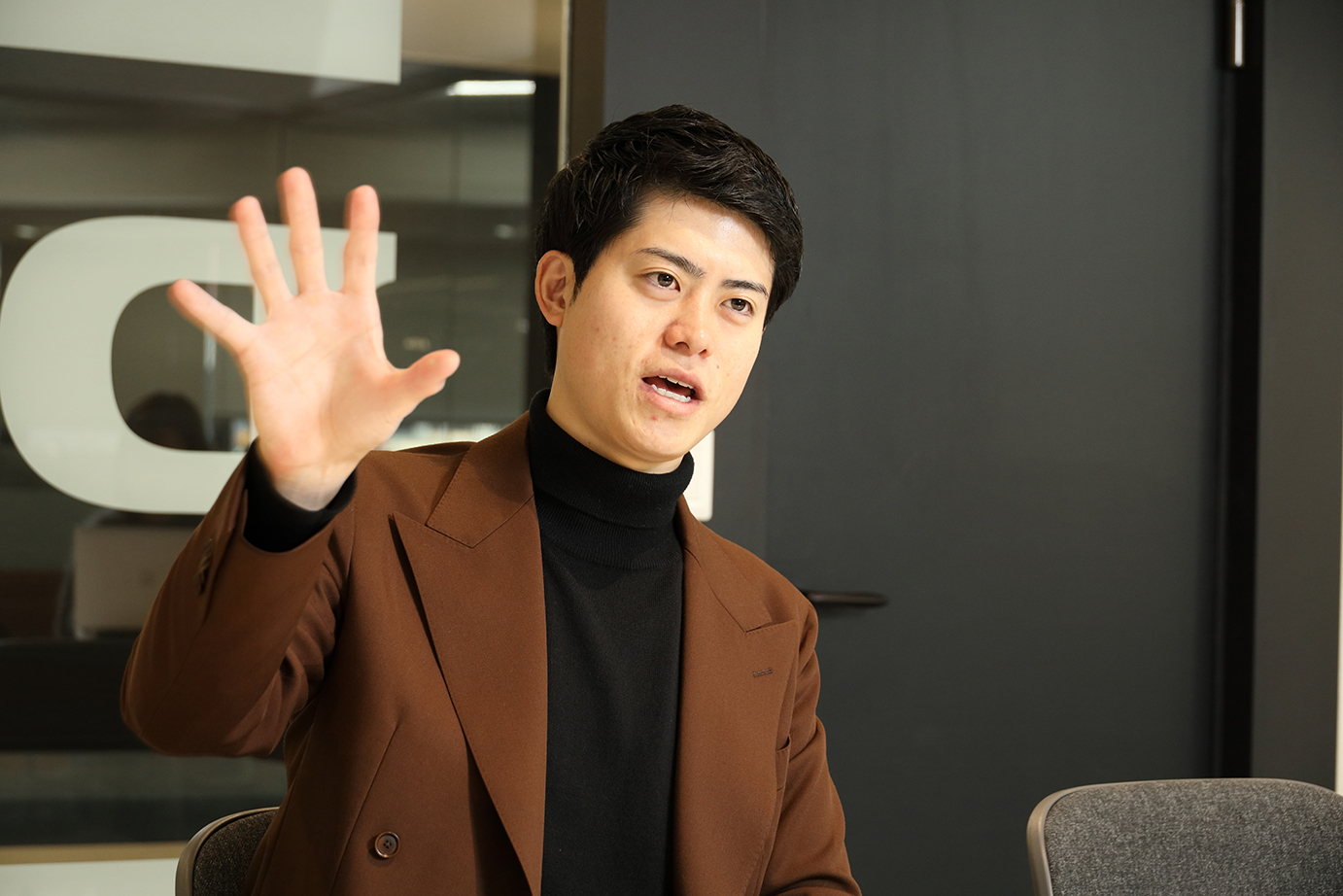
おかだ・しょうご 大阪大学卒業後、新卒でマッキンゼー・アンド・カンパニーに入社。日本企業の海外進出、 海外企業の日本市場戦略立案等、数々のプロジェクトに従事。同社を退社後、2016年9月にプログリット創業。英語コーチングサービス「プログリット」を主軸とし、サブスク型英語学習サービス「シャドテン」も展開。22年9月、東証グロース市場に上場した。
最初から3年と決めてマッキンゼー入社
―― 岡田さんは大阪大学を卒業したあと、新卒でマッキンゼー・アンド・カンパニーに入社しています。もともとコンサルティング業界に興味があったのですか。
岡田 小さな専門商社を経営していた父の姿を見ていたこともあり、大学時代にはいずれ起業したいと思っていました。ですから最初に入る会社は、ずっとそこで頑張るというより、自分の成長に資する企業を選ぼうとは考えていました。その視点で就職先を見ると、外資系なら厳しい環境で、かつ優秀な人に囲まれて仕事ができることが分かった。そうなるとやはりコンサルか投資銀行というのが選択肢になり、マッキンゼーに入社。最初から修行のつもりで、長くても3年間、と決めていました。
―― ということは、3年間、ずっと次のビジネスのことを考えて働いていたわけですね。
岡田 ところが、入社したら起業することは全然忘れてしまって、仕事に没頭していました。マッキンゼーの社員として、いかにお客さまに価値を提供するのかだけを考える日々で、自分を成長させるためにはどうするかを考えるよりも、本当に日々お客さまに向き合って仕事をしていたという感じですね。
―― 最初の仕事はどんなものでした?
岡田 マッキンゼーの仕事は、プロジェクトごとにマネージャーが一人いて、その下にビジネスアナリスト、つまりコンサルタントが2、3人いてチームをつくります。最初はその一番下っ端として、エクセルでデータを分析し、資料としてのパワーポイントを作成するというのが与えられた役割でした。何十枚ものパワーポイントを、毎日つくり続けていたのが1年目でした。
ただマッキンゼーの場合、クライアントに対してはプロフェッショナルであることが求められます。僕は入社して2週間の研修後、最初の仕事が製造業のコンサルだったのですが、その初日に上司から「岡田は製造業のプロフェッショナルですから」とクライアントに紹介されました。お客さまは僕がプロだと思っていますから、いろいろと質問してくるわけです。ところが僕にしてみれば「2週間前まで学生だったんですけど」。だけどクライアントからは相当な金額を頂いています。ですから期待に応えなければならない。そのプレッシャーを日々感じながら 仕事をしていました。
マッキンゼーの場合、多くは3カ月か6カ月でプロジェクトは終了します。すると金曜日に、次の月曜日からのクライアント企業とプロジェクト内容が送られてくる。ですから土日は必死です。本屋に行ってその業界に関する本を手当たり次第に買ってきて必死になって勉強する。そして月曜日にはプロの顔をしてクライアント企業に赴きます。
マッキンゼーには2年3カ月在職しましたが、その間、製造業から商社や製薬、銀行、あとは公共的なインフラ系などさまざまな業界を担当しました。プロジェクトの内容もコスト削減から戦略立案、M&Aと、何でもやりました。
シンガポールの研修で思い出した自分の使命
―― クライアントやプロジェクトの内容はどうやって決まるのですか。
岡田 プロジェクトに自分で手を挙げて、採用されれば担当となります。僕の場合なら、まずそのプロジェクトがインタレスティングであるかどうか。それともう一つはそのリーダーと一緒に働きたいかどうかで決めていました。やはり誰と働くかによって、成長に寄与するかどうか大きく変わりますから。
―― 自分の時間を持つことはできました?
岡田 マッキンゼー時代は奴隷のように働いていました。朝はだいたい8時半か9時にクライアント企業に出社します。そこの社員の方々の終業時間となる午後6時や7時まで一緒に働きます。それからマッキンゼーのオフィスに戻り、夕食を簡単に済ませて午後11時か12時まで働く、という毎日でした。土日も仕事のことが頭を離れることはなかったですね。というのも、自分の実力不足が分かっていたので、そのぐらいやらないとお客さまにご納得いただけないと思っていたからです。
―― どういうところが実力不足だったのでしょう。
岡田 先輩とはレベルが違いましたから。優秀なマッキンゼー社員は、経験もあるし論理的思考法も身についているので、物事を最後まで読むことができる。一種の仮説思考です。
マッキンゼーの仕事は、基本的に3カ月目の最後の日に、厚い資料をつくり、それをプレゼンテーションして終わります。これを3カ月かけてヒアリングして作成するわけです。ところが優秀な人は、何も分析していないにもかかわらず、初日の段階で90日後にプレゼンする内容が頭の中にすでに出来上がっている。それを僕ら下っ端は3カ月かけて検証しているようなものです。そして実際、そのプレゼンは間違っていない。そんな思いを何度もしました。それにエクセルのスピードも半端ではないし、パワーポイントのクオリティがまるで違う。ですからそれを追いかけて、一生懸命仕事する日々でした。
―― 追いかけているうちに、成長したなと感じるようになりましたか。
岡田 自分の中では1年ほどで相当変わりました。外から見たら五十歩百歩の世界かもしれませんが。
端的に言えば、仕事のマネジメントができるようになった。例えば仕事を頼まれた時に、これとこれをやればこのくらいの時間でできるなと分かるようになり、やってみたら実際にその通りに実行できる。これが最初の頃なら、何時間かかる作業なのかも分からないし計画性もない。とにかく必死に仕事するしかないという状況でした。
あとは先輩と議論をしていても、最初の頃は自信を持って話していても、後になるとそれがいかに薄っぺらだったかが分かってくる。そんな恥ずかしい経験をしながら、そのうち先輩が自分の意見に耳を傾けてくれるようになってくる。それは感じていました。
―― そんな生活をしながら、最初に定めた期限の3年間が近づいてきます。どんな思いでした?
岡田 そのことは完全に忘れていました。とにかくマッキンゼーの仕事が楽しかったですから。仕事は大変ですが、最終日にお客さまに「ありがとう」と言ってもらえることが喜びでしたし、先輩・同僚・後輩、みんな大好きでした。
ところが入社1年半がたった頃、シンガポールで世界の2年目社員を集めた研修がありました。同期なのに言葉も違うし文化も違う。それでもマッキンゼーのカルチャ―はみんな共有しているという不思議な集まりでした。その研修で、「マッキンゼーで働くということがあなたのやりたいことなんですか」と言われて、「そや、忘れてた」と。自分は起業するためにここにきたことを思い出しました。それで半年後にはマッキンゼーを辞めました。入社してから2年3カ月がたっていました。
若い時代だからこそ人生を懸ける働き方
―― 起業を決意してから辞めるまでの半年間は何をしていたのでしょう。
岡田 マッキンゼーの仕事をやりながら、起業のアイデアをずっと考えていました。そうしたところ、アイデアが天から降りてきた。これをやるのが自分の使命だ、そう思って会社を辞めました。ところが、いざ事業計画を立ててみると、これはうまくいかないことが分かってきた。そこで急遽、別の事業を考え、1週間後には今のプログリットにつながる英語コーチングというビジネスモデルを考えました。
なぜ英語コーチングだったかというと、自分自身、英語が話せるようになったことで人生が豊かになったという経験があります。もし英語ができなかったらマッキンゼーにも入れませんでした。ただその一方で、自分の英語力がそれほどでもないという自覚もあった。僕と同じように英語で苦しんでいる人はたくさんいる。それなのにその人たちをサポートするサービスが当時はまだ存在していないことに気づきました。
―― 英会話スクールはいくらでもありました。
岡田 確かにそうですが、どこもちょっと物足りなかった。英会話を学ぶことはできるかもしれませんが、なかなか継続できない。だから成果が上がらない。そこでプログリットではレッスンに対価を頂くのではなく、その人にとって何が最適な学習方法なのか、どうすれば継続できるのかにフォーカスし、確実に英語力を向上させるという価値に対価を頂こうと決めたのです。
―― 起業にあたりマッキンゼーの経験は役に立ちました?
岡田 プログリットの基本的なスキームはマッキンゼーと同じなんです。マッキンゼーの場合、3カ月で会社や組織を変えるわけです。プログリットの場合は現状分析をして何が課題かを提示して、その課題のソリューション戦略を考え、実行してもらい、短期間で英語力を向上させる。企業か個人かの違いはありますが一緒です。
―― 立ち上げたプログリットは創業6年目の2022年に上場を果たし、現在は社員数も200人以上に膨れ上がりました。4月には新卒の新人も入ってきますが、彼らには、かつての岡田さんのように馬車馬のように働いてもらうのですか。
岡田 われわれは上場企業ですから、僕がマッキンゼーに入った時のように働いてもらうのは難しいでしょうね。ただ、若い頃に必死になって働くことは、けっして悪いことではないと思いますし、そうした機会が与えられなかったとしたら、むしろかわいそうだと思います。
人生を懸けるぐらいのコミットをしないと、その仕事が楽しいのかどうかも分からないし、自分に向いているかどうかも判断できない。それに一つのことにコミットしてきた人というのは、転職するにしても市場価値はものすごく高い。ですから、入社してすぐに、自分に合わないと思って辞めてしまうのは、もったいないな、と思いますね。




