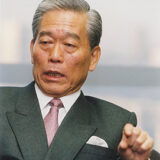少し前まで、セブン&アイ・ホールディングスと言えば、流通業界の中で数少ない勝ち組だった。しかしここに来て業績が悪化。さらには海外の同業者からM&Aを仕掛けられるも対応は後手に回る。9年前、権勢を欲しいままにしていた鈴木敏文会長(当時)を辞任に追い込んだ井阪隆一社長もその座を追われることになった。文=下田健司(雑誌『経済界』2025年7月号より)
セブンイレブンの生みの親が総会屋事件で実権を掌握

鈴木敏文は1992年、イトーヨーカ堂社長に就いた。総会屋への利益供与という商法違反容疑でイトーヨーカ堂の役員と幹部社員が逮捕されたため、伊藤雅俊社長が引責辞任し相談役に退き、副社長だった鈴木が社長に昇格したのである。
社会問題化していた総会屋については、81年に商法が改正され規制が強化されていた。80年代には伊勢丹、そごう、パルコなど流通大手の商法違反事件が相次いだ。多くの上場企業が総会屋と関係を持っていた時代とはいえ、商人道を説き、信用第一で誠実さや真面目さを大切にしてきた伊藤だっただけに事件が与えた衝撃は大きく、痛恨の出来事であった。
イトーヨーカ堂は、伊藤の叔父、吉川敏雄が20年に開業した洋品店「羊華堂」(東京・浅草)に始まる。58年にヨーカ堂(現イトーヨーカ堂)を設立。61年にチェーン展開を開始した。旺盛な国内消費を追い風にイトーヨーカ堂は成長を遂げる。経常利益は80年度に三越を抜いて小売業界でトップに立つなど、業界屈指の高収益企業となった。
だが、82年2月期上期に創業来初めて経常減益に陥った。そこで取り組み始めたのが業務改革(略称「業革」)だ。業革の陣頭指揮を執ったのが、当時常務だった鈴木だ。コンビニエンスストア子会社セブン-イレブン・ジャパンの実質的創業者である鈴木は、セブン-イレブンで成功した在庫管理の手法をイトーヨーカ堂に持ち込んだ。商品の販売動向を単品ベースで把握する単品管理によって、死に筋を排除し、売れ筋を積極投入する。これによって資金回転の向上を図るのである。業革の結果、イトーヨーカ堂は収益を回復させていった。
こうして実績を積み上げていた鈴木はイトーヨーカ堂社長に就き、名実ともにグループのトップの座についた。
鈴木敏文が次々と打ち出した新機軸

鈴木は63年、東京出版販売(現トーハン)からイトーヨーカ堂に転職した。メーカーの価格支配を打ち破り消費者主権を確立するという流通革命を掲げた中内㓛が率いるダイエーを筆頭にスーパーが台頭していたが、当時イトーヨーカ堂はまだ数店舗を展開するスーパーにすぎなかった。
入社後、人事畑を歩んだ鈴木は早くから頭角を現した。伊藤から高く評価され、71年に取締役に就いた。
そんな中、イトーヨーカ堂は新規事業開発に乗り出す。新規事業を検討するため設けられた「業務開発室」の責任者となったのが人事・広報を担当していた鈴木だった。鈴木が目を付けたのは米国視察で見かけたコンビニだった。
イトーヨーカ堂は大型店の出店に際し中小小売店の反対を受けていた。その矢面に立たされていた鈴木は、米国で目にしたコンビニを日本に持ち込み、中小小売店の低生産性を改善し共存共栄ができればビジネス機会となると考えた。コンビニ事業に対しては社内外から反対意見が圧倒的だったが、それを押し切ってでもやる価値があると鈴木は判断、伊藤も承認した。
73年、イトーヨーカ堂はヨークセブン(現セブン-イレブン・ジャパン)を設立し伊藤が社長、鈴木が専務に就いた。米サウスランド社とエリアフランチャイズ契約を結び、翌74年、東京・豊洲に1号店を出店、フランチャイズ方式によるセブン-イレブンの展開を開始した。
鈴木は流通業界の常識にとらわれない数々の新基軸を打ち出していった。
商品供給の効率化を図るため、ベンダーの集約化や、流通系列を超えた共同配送に取り組んだほか、商流と物流を分離し業務効率化やコスト削減を図った。業界に先駆けて、取引先との受発注を簡素化するオンラインシステムや、商品の販売動向を単品ごとに把握するためのPOSシステムなど情報システムの整備にも取り組んでいる。
セブン-イレブン創業時と同じように否定的な意見が多かったのが銀行業への進出だ。2001年にイトーヨーカ堂と共同でアイワイバンク銀行(現セブン銀行)を設立し、セブン-イレブン店舗にATM(現金自動預け払い機)を設置。ATMでの出入金にサービスを特化し、その手数料だけを収益源とする決済専門銀行を目指した。イトーヨーカ堂とセブン-イレブン・ジャパンによる銀行設立は異業種からの銀行参入自由化の第1号となった。
コングロマリット化を始めたのが05年。イトーヨーカ堂は傘下のセブン-イレブン・ジャパン、デニーズジャパンと経営統合し、純粋持ち株会社セブン&アイ・ホールディングスを設立した。
当時、フジテレビジョンを筆頭株主とする旧ニッポン放送の株式をライブドアが大量取得し、資本のねじれによる買収リスクが高まっていた。イトーヨーカ堂とセブン-イレブン・ジャパンにおいても、時価総額は親会社のイトーヨーカ堂のほうが小さかった。セブン&アイの設立はこの資本のねじれを解消し買収リスクを回避のねらいもあった。
セブン&アイ設立の翌年には、そごう、西武百貨店を傘下に持つミレニアムリテイリング(現そごう・西武)を買収し、スーパー、コンビニ、外食に百貨店を加えた総合小売グループとなり、当時として国内で最大、世界でもトップ10に入る売上規模を誇った。
そごう・西武の買収の背景には、鈴木と伊藤の百貨店への憧れがあったといわれている。百貨店商品をイトーヨーカ堂に持ち込もうと試みたが、百貨店業界の商慣行の壁は厚く、実現は難しかった。
百貨店に続いて専門店の買収も手がけていった。07年に赤ちゃん本舗を子会社化。13年にカタログ通販のニッセンホールディングスや、生活雑貨店「フランフラン」を展開するバルスと資本業務提携。15年にはセレクトショップのバーニーズジャパンを完全子会社化した。
鈴木はグループ各社の店舗とネットを融合するオムニチャネル構想を打ち出し、15年にはサイト「オムニセブン」を立ち上げた。実現するために独自商品の開発が不可欠と考え、買収した専門店の活用を目指したがあては外れた。オムニセブンの業績は伸び悩んだ。新規事業を成功に導いてきた鈴木だったが、オムニセブンは23年に終了した。
更迭されたはずが生き残った逆転人事
2016年、鈴木は会長兼CEO(最高経営責任者)を退くことを突如表明し、セブン&アイに激震が走った。自ら提案した、セブン-イレブン・ジャパン社長だった井阪隆一を更迭する人事案が取締役会で否決され、信任を失ったと受け止めたのである。
鈴木から伝えられた内示をいったん受け入れた井阪だったが、「5期連続で最高益を更新している」などとして態度を急変させた。井阪をセブン-イレブン・ジャパン社長に引き上げたのも鈴木だったが、記者会見の場で井阪について「新しいものが出てこない」などと手厳しく評した。井阪が態度を急変させた背景には伊藤の存在があったとされ、セブン&アイの誠実な企業イメージからは想像できないお家騒動は、かつての総会屋事件を思い出させる“事件“だった。
強力なリーダーシップで会社を成功に導き長期政権になると後継者が育たなくなる。社長交代はどんどん難しい判断になっていく。
伊藤から鈴木への社長交代は、総会屋事件という不測の事態を収拾するためだった。当時は伊藤の長男の裕久がイトーヨーカ堂に在籍しており、後継者候補の一人と目されていた。伊藤が、平時に鈴木への社長交代か世襲かを決断できたかどうか。総会屋事件が起きなければ社長交代を決断できなかったのかもしれない。同じように、鈴木も創業家との確執があったことで辞意を決断できたと言える。
後継者を育てることはできなかった鈴木が重用したのは二男の康弘だった。康弘は富士通やソフトバンクを経て、イー・ショッピング・ブックス(ソフトバンク、セブン-イレブン・ジャパン、トーハン、ヤフーが1999年に設立した合弁会社)の社長に2000年に就いた。06年にセブン-イレブン・ジャパンの子会社となりセブン&アイ傘下に入ると、グループのデジタル戦略を主導するようになる。14年にセブン&アイ執行役員CIO(最高情報責任者)に就き、15年にはセブン&アイ取締役に昇格。鈴木が康弘に世襲しようとしているのではないかという臆測が広がった。その康弘も16年、取締役を退任している。
鈴木退任後の新しい経営体制で社長に就いた井阪は25年5月に退任する。
井阪が社長として取り組んだのは成長戦略と構造改革だ。
成長戦略の柱とするコンビニ事業については、M&A(合併・買収)によりグローバル展開を加速する方針を掲げた。18年に30億ドル超を投じて米中堅コンビニのスノコから1030店を取得。21年には210億ドルという巨費を投じて米コンビニ大手のスピードウェイを買収している“。
構造改革の焦点は、グループの足を引っ張っていたイトーヨーカ堂やそごう・西武の扱いだった。社長就任当初、イトーヨーカ堂については店舗建て替えによる不動産再開発などの活性化策を打ち出すにとどまり、米投資ファンドから切り離しを求められていたそごう・西武についても踏み込み不足だった。
本格的に“負の遺産”処理が動き始めたのが22年だ。まず、そごう・西武については売却について米投資ファンドのフォートレス・インベストメント・グループと合意する。だが、売却をめぐってはセブン&アイによる利害関係者への根回し不足のほか、売却後の売場構成や雇用確保でそごう・西武労組との調整が難航。雇用維持を求める労組と会社側の対立は西武池袋本店でのストライキに発展した。売却の実行日を2度延期するなど売却交渉は長期化し、当初23年2月を予定していた売却の実行日は23年9月にずれ込んだ。
イトーヨーカ堂については、24年10月にスーパーや専門店など非中核事業を束ねる中間持ち株会社ヨーク・ホールディングスを設立。25年3月、ヨークの株式売却について米投資ファンドのベインキャピタルと売却額8147億円で最終契約を結んだ。
セブン&アイはベインキャピタルにヨーク全株式を売却後、創業家を含む40%の保有比率分をヨークに再出資する。ヨークは外部資本の下でスーパー事業を立て直し、早期の新規株式公開を目指す計画だ。
M&Aに業績悪化で無念の社長交代へ
こうして井阪は鈴木が手をつけられなかった構造改革にめどをつけたが、カナダのコンビニ大手アリマンタシォン・クシュタール(ACT)による買収提案という難題に直面し、解決策を見いだせないまま社長を退く。
ACTの買収提案に対して、セブン&アイ創業家は非上場化で対抗しようとしたが、8兆円を超えるとされる資金調達のめどが立たず断念した。セブン&アイは、企業価値を高め自主路線を堅持するため、ヨークの売却だけでなく、米セブン-イレブン・インクを26年下半期までに上場させるほか、金融事業についてセブン銀行株の保有比率を40%未満に引き下げ非連結化を進めるなど、資本構造・事業の変革を進めるとしている。
ACTとの買収協議は、米国事業などで主張に隔たりがあり難航しているが、ACTは日本法人を設立したり、日本語サイトを開設したりするなど買収意欲は衰えていない。
井阪に代わって次期社長に予定されているのが、社外取締役のスティーブン・ヘイズ・デイカスだ。グループ初の外国人社長で、米航空機メーカー、会計事務所、米食品メーカー、ファーストリテイリング、米ウォルマート、西友、スシローグローバルホールディングスなどを経て、22年セブン&アイの社外取締役に就いた。24年からは取締役会議長を務めるほか、ACTの買収提案を検討する特別委員会の委員長を務める。
社長交代人事の発表後、米投資ファンドがセブン&アイに書簡を送り、特別委員会の委員長や、次期社長を検討する指名委員会の委員を務めたことに利益相反の疑いがあるとし、社長人事に反対し、買収提案の再考も求めた。株主総会で次期社長人事に反対する意向も示している。
ACTの買収提案で揺れるセブン&アイ。2025年2月期連結決算で、2期連続の最終減益となり、業績立て直しも急務だ。次期社長にとって多難の船出となる。(敬称略)