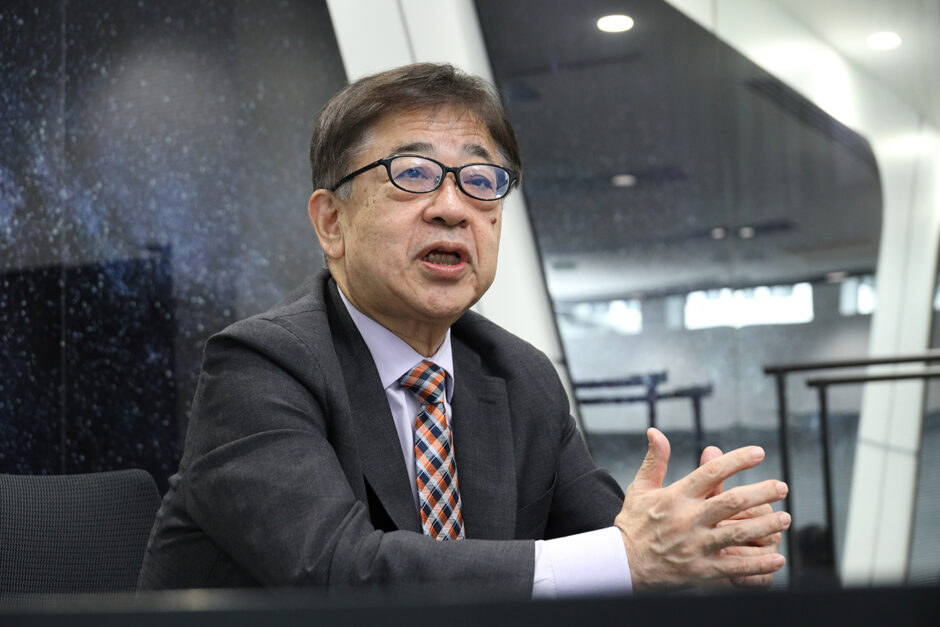スペースデブリ(宇宙ごみ)の回収をはじめとする軌道上ビジネスを手掛け、2024年6月に上場を果たしたアストロスケールホールディングス。その日本子会社を指揮するのが、世界の宇宙産業の現場を知る加藤英毅社長だ。「一度は日本を見限った」と語る加藤氏が、日本の宇宙産業に戻った理由とは。聞き手=小林千華 Photo=横溝 敦(雑誌『経済界』2025年8月号より)
加藤英毅 アストロスケールのプロフィール

かとう・ひでき 愛知県名古屋市生まれ。三菱電機の宇宙部門で勤務した後、ロッキード・マーティン、ゼネラル・エレクトリックなど海外の宇宙産業の現場を渡り歩く。仏タレス・アレーニア・スペース社では、アジア地域の統括、フランス本社の販売部門統括、北米支社長を歴任。2015年、アメリカでコンサルティング会社 HISe, Inc.を創設。23年2月、アストロスケール社長に就任。
ビジネスの3本柱を構築し会社の体制を強化する
―― アストロスケールHDの日本子会社とのことですが、具体的にどんな役割を担っているのでしょうか。
加藤 アストロスケールHDの100%子会社として、当社のほかに米国、イギリス、フランスなどに会社があり、当社は日本子会社として日本、アジア、中東までのサービス展開を担っています。
メインで手掛けているのは人工衛星の製造・開発・運用。昨年スペースデブリに約15メートルの距離まで接近し、写真撮影に成功した人工衛星「ADRAS-J」も、当社が開発・運用したものです。
現在社内では、4つのプロジェクトが走っています。1つ目はADRAS-Jの後継機「ADRAS-J2」。ADRAS-Jはスペースデブリに接近して写真を撮ることをミッションとしていましたが、J2ではそれに加え、実際に捕獲、除去を目指します。2つ目は「「ISSA-J1」といって、人工衛星のデブリを観測するプロジェクトです。そして3つ目はまだ正式契約には至っていませんが、人工衛星への燃料補給プロジェクト。これら3つは政府の支援を受けた案件です。
4つ目は今年に入って防衛省から受注した、「SDA(宇宙領域把握)」に関するプロジェクト。静止軌道上での宇宙監視、情報収集、宇宙作戦能力の向上に向けた人工衛星の試作機を製作するものです。
どれもまだ設計段階で人手がかかるので、今社内はかなり忙しい状況です。しかし複数のプロジェクトを同時に進めることで会社としても力が付いてきますし、サプライチェーンなどを共通化できるといったメリットもあります。
―― アストロスケールというと、「スペースデブリ除去の会社」と認識している人が多いように思えます。
加藤 そういったイメージを持たれるのも無理はありません。しかしスペースデブリ除去だけでなく、先ほど説明したようなさまざまな軌道上サービスを手掛けるのが当社です。
スペースデブリ除去というと、デブリの捕獲、除去方法に目がいきがちですが、そもそもデブリに近付くこと自体がとても難しいんです。デブリもわれわれの宇宙機も同じ速度で軌道上を回るので、近付くことも離れることも難しい。逆に言えば、軌道上の対象物に近付けるようになることで、スペースデブリ除去、人工衛星への燃料補給、将来的には人工衛星の部品交換など、やれることの幅が一気に広がります。
その意味で、昨年ADRAS-Jが世界で初めてデブリまで15メートルの距離に接近できたことは、大きな功績でした。
―― そうした技術を用いて、どのようなビジネス展開をしていますか。
加藤 事業としては、3本の柱の構築を急いできました。英語で言えばCivil(官庁系)、Defense(防衛)、Commercial(商業)の3本柱です。前2つについては既にある程度形ができつつありますが、今後強化していかなければならないのが3つ目、民間企業が顧客になるビジネスです。
考えられるものとしては、例えば通信衛星に向けたサービス。人工衛星の寿命は約15年といわれていますが、1台の人工衛星を作って打ち上げて運用するのに、15年間で約300億円かかるといわれます。軌道上での燃料補給や部品交換などが実現できれば、運用期間が延び、実質的なコストダウンにつなげられます。
燃料補給事業についてはまだ開発を始めたところなので、実証に至るのは2030年頃になるでしょう。その結果次第でどう販売できるかという議論になるので、時間はかかりますが着々と進めていきます。
宇宙バブルもいずれはじける 今企業が考えるべきことは
―― そもそも加藤さんは、どういった経緯でアストロスケールに参画したのでしょう。
加藤 私は宇宙業界での経験は長いですが、海外で過ごした期間がほとんどです。
かつては三菱電機の宇宙部門で営業業務に従事していました。しかし、日米貿易摩擦の解消に向け、1990年に日米衛星調達合意が締結され、人工衛星の調達は国際競争入札が原則となり、当時の日本メーカーの実力では現実的に選ばれづらい状況になってしまいました。
私は、当時三菱電機で海外に向けて衛星搭載機器の市場を開拓していたのですが、このまま続けても結局アメリカの下請けのままだろうと。そこで、たまたま引きのあったアメリカの会社に移ることにしました。
そこからはアメリカやフランスの会社を渡り歩きました。中国・北京に駐在してアジア市場の責任を持ち、現地の宇宙ビジネスを間近で見た時期もありますし、フランスにも駐在しました。最終的に2015年、アメリカで宇宙および電気通信分野のコンサルティング会社を立ち上げ、7年ほど活動していた中でアストロスケールから声がかかった、という経緯です。実は最初はお断りしたのですが。
―― どうしてですか。
加藤 今更日本に戻って新しい仕事を始めるのはけっこう力がいるなと。しかし、コンサルの立場で半年ほど関わる中で血が騒いでしまったというか、結局お受けすることにしました。アストロスケールは新興企業ながら、一定の戦略に沿って筋道を立てて進んでいる印象が持てたことも大きかったです。
HD創業者の岡田(光信CEO)の印象も、正直最初は「ノリのいい人だな」と(笑)。しかしすぐに、華々しくダイナミックに戦略を描く岡田と、その戦略を形にして土台を固めていく私とで、良い役割分担ができると感じるようになりました。
―― 加藤さんが社長に就任した時点で、アストロスケール内はどのような状況だったのでしょう。
_AS_c06_A_4K.0001.jpg)
加藤 日本子会社の従業員数は当時100人程度でしたが、その全員がADRAS-Jのプロジェクトにかかりきりでした。もちろんADRAS-Jは重要なプロジェクトですが、会社として形を成していくにはもっと多角的な視点が必要だと呼びかけてきました。その結果、今は4つのプロジェクトを同時進行させられるようになり、会社としても強くなったと思います。
―― 海外での経験を経て、日本の宇宙ビジネスの現状をどう見ていますか。
加藤 率直に、日本はよく頑張ってきたと思います。私は一度日本を見限ったわけですが、今見てみれば宇宙産業の中でも日本が健闘している分野が多々あって、めげずによく頑張ったなと思います。しかし、われわれの軌道上サービスなどでは日本が世界の先端を走っていますが、ロケットや人工衛星といった従来型のサービスでは出遅れた感があります。その原因の一つには、やはり先ほどお話ししたように、海外の入る隙を与えてしまったことがあると私には思えます。
国内でも宇宙産業への注目度がかつてないほど高まっている今、大事なことは、今後いかにビジネスの方に目を向けていくかだと思います。日本ではどうしても、ハードウェアの開発といった目に見える結果が注目されがちで、先端技術の開発は進みやすいけれど、それをうまくビジネスとして商用化していく面では弱いように感じます。
その点はやはりアメリカなどが進んでいますね。SpaceXがかつてない低コストでのロケット打ち上げを実現したことも、従来の常識を壊して商用化の枠組みをつくったという意味ではすごいことです。
―― 日本の宇宙ビジネスに、今何が必要でしょうか。
加藤 アメリカでは00年代からSpaceXなどを皮切りに、民間企業が宇宙ビジネスを主導する「ニュースペース」という潮流ができました。資金集めのためにSPAC(特別買収目的会社)上場も盛んに行われましたが、宇宙ビジネスバブルが崩壊して、今や企業が淘汰されるフェーズに来ています。
日本ではSPAC制度は認められていないので全く同じ道をたどることはないですが、いずれ資金の続かない企業が淘汰される時期は来ると思います。今は宇宙戦略基金などもあって資金がつきやすい状況ですが、企業側もそうしたプラスアルファの資金でどこまでやるのか、それがなくなればどう事業を維持していくのか常に意識して、締めるべきところは締めていく必要があると思います。
しかし新興企業にはどうも、リスクを考えて止めるとか締めるとかいう発想を持ってはいけないような感じがありますよね。アストロスケールでも、そんな新興企業らしい勢いと堅実さのバランスをどうとるべきか、よく議論します。その中で私はある意味「伝道師」のような形で、若い従業員たちをケアしながら事業を指揮していくのが役割だと思っています。