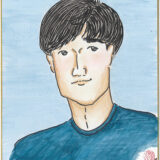2025年6月、日本の基幹産業である自動車業界の時価総額をエンタメ産業が逆転した。今後の日本を支えるのはエンタメだ。「信長の野望」や「真・三國無双」など大人気シリーズを送り出してきたコーエーテクモホールディングスの鯉沼久史社長に、ゲームビジネスの勘所を聞いた。聞き手=和田一樹 Photo=小野さやか(雑誌『経済界』2026年1月号より)
鯉沼久史 コーエーテクモホールディングスのプロフィール

こいぬま・ひさし 1971年生まれ。94年に東京電機大学を卒業し、光栄(現コーエーテクモゲームス)に入社。プログラマーを経て「戦国無双シリーズ」や「ガンダム無双シリーズ」などのプロデューサーを務める。2015年4月からはコーエーテクモゲームス社長COO、25年6月からコーエーテクモホールディングス社長CEO(現職)。
ガバナンスの本質は社員の幸せにある
―― 2025年6月、コーエーテクモホールディングスの社長CEOに就任し、半年弱が経過しました。
鯉沼 ホールディングスの社長としては1年目ですが、15年から中核事業会社であるコーエーテクモゲームスの社長を務めてきました。自分としては約10年をかけてコーエーテクモグループ全体の経営も少しずつ見てきましたから、新社長という感覚は薄いかもしれません。
―― コーエーテクモといえば、創業者である襟川陽一さん、恵子さんご夫妻の存在は大きかったはずです。圧倒的な求心力のあるオーナーから経営を引き継ぐことに難しさは感じませんでしたか。
鯉沼 たしかに一般的には、サラリーマン社長の立場から見ると圧倒的なオーナーがいない会社の方が経営はしやすいのかもしれません。ただ、私の場合は1994年に新卒で光栄(現コーエーゲームス)に入社し、襟川ご夫妻というオーナーがいることが当たり前の環境で仕事をしてきましたから、オーナーや社長も一つの役割や機能のようなものと捉えており、難しさはそれほど感じていません。
むしろ、今後のコーエーテクモの経営体制としては、監督と執行の分離を着実に進めていくことが重要だと思っています。オーナーには執行から離れた後も株主として会社に関与していただいており、過渡期の経営体制といえます。私の大きな役割の一つは、オーナー経営からサラリーマン経営に移行させることだと理解しています。
―― コーポレートガバナンスの在り方を変えていく際、思わぬ結果を招く可能性はあります。進んでいる方向の正しさは、業績や株価で測りますか。
鯉沼 形式的な話に限って言えば、資本コストを意識した経営が近年特に求められているように、プライム上場企業としてある程度のベストな形はあります。当然それはそれとして参考にしていますし、取り組みも進めているところです。
しかし、本質は社員が幸せであることだと思います。人材こそが当社グループにとって最大の資産ですので、どんなガバナンス体制であっても、社員が働きやすく信頼される会社であることがベースです。そして、従来から掲げてきた目標である「世界No.1のデジタルエンタテインメントカンパニー」を目指して成長を続けていく。すると利益も必ずついてくるはずですから、それを株主のみなさまに還元する。この循環が基本だと考えています。
―― 事業を成長させるために、どんな部分を変えていきますか。
鯉沼 何かを大きく変えるよりも、まずはこれまで受け継がれてきたイズムをしっかりと次の世代に引き継いでいくことを心掛けています。というのも、当社がビジョンとしてずっと掲げてきた「世界No.1のデジタルエンタテインメントカンパニー」というのは非常に大きな目標ですので、変えることなくこれからも目指していきたいからです。
組織の面で言っても、コーエーテクモは、2009年にコーエーとテクモが経営統合し、11年にガストが加わり、それぞれの源流やIPを持つゲーム会社が一緒になってやってきた歴史を持っています。各社のIPを生かすために導入したのが「ブランド制」です。このスタイルは私個人としても強い思い入れがありますので、しっかりと守っていきたい哲学だと感じています。
マーケットを見極めれば適切な利益は積み上がる
―― 複数のブランドを独立させた開発体制としたのはなぜでしょうか。
鯉沼 例えば大きな売り上げを期待できるブランドだけに集約したとします。売れる作品や、一定の見込みを立てやすいシリーズものなどに集中すれば、ある意味で効率はいいのかもしれません。でも、その状況が長く続けば、やがて同じようなクリエーティブしかアウトプットできない組織になってしまうことを懸念しています。
だからこそ、各ブランド、各チームがそれぞれ得意とするゲームを作り続けられる体制はしっかりと守ってあげたい。10万本、20万本売れるゲームから500万本売れるゲームまで、いろんなプロダクトを生み出せる、ゲームの総合商社のような会社であり続けたいと考えています。
―― プロダクトに占めるメガヒットの割合が高ければいいというわけではないのですね。
鯉沼 全てのプロダクトに100億円のバジェットを用意することは難しいですから、マーケットのサイズに応じて適正なプロダクトを送り出していくことが重要です。社内では、プロジェクトごとの営業利益は30%を目指そうという話をよくします。
マーケットサイズを見誤らなければメガヒットタイトルでなくともきっちり利益を積み上げることができますし、ユーザーは多くの人が好むゲームばかりを求めているわけではないんです。ある意味、ニッチでマニアックなゲームだとしても、楽しんでくれる層がいると思えればそこにゲームを届けたい。私自身もひとりのゲーム好きとして、できるだけいろんなゲームで遊びたいという気持ちが根っこにあるのだと思います(笑)。
これは経営的な観点でも重要です。ゲーム単体の利益は大きく見込んでいなくてもマーチャンダイジングでしっかり稼ぐタイトルがあったり、IPとして他ジャンルとのコラボレーションで大きく跳ねるタイトルもあったりするので、そういう可能性も大事にしたいと思っています。ゲームを売ることだけがゲーム会社の経営ではないということです。

広がり続けるゲーム産業 ビジネスチャンスをつかむ
―― ゲームビジネスの勘所はなんでしょうか。
鯉沼 一番の核はユーザーが求めている以上のゲームを出せるかどうかです。新作かシリーズものかは問わず、遊ぶ人の期待を良い方向に裏切るプロダクトが出てこないとゲーム会社は続かないでしょう。そこは最低限、求められる部分です。
加えて、他ジャンルとのコラボも重要な時代になっています。これまで小説や漫画、アニメから生まれたIPを基軸にテーマパークやグッズ展開、メディアミックスなどが広がっていくケースが目立っていました。ところが、近年はゲームのIPから生まれた映画がヒットしたり、遊園地とコラボがあったり、グッズが大ヒットしたりすることが増えています。これはゲームという産業が持つポテンシャルが高まっているからこそだと思っていまして、今後も大きなビジネスチャンスであり続けると考えています。
当社は社員のほとんどがゲームを作ることが大好きな人たちですので、まずはゲーム作りの面で柱を生み出すことを核にし、ビジネスを広げる面は社長である私がリードしていければいいなと思っています。
―― コーエーテクモのゲーム作りの特色は何でしょうか。
鯉沼 基本的には自社で開発を行う企業であること。そして、新卒入社の社員が多いことだと思います。プロパー社員として新卒から育て、当社にロイヤリティを持ってもらい、一緒になってモノづくりをしていく。近年は採用を積極的に行っていることもあって、毎年全社員の10%弱に相当する数の新卒社員が入社してきますから、現場には人材育成の面で負担をかけているとは思います。ですが、仕事を教え、教わりする中で人間関係が構築され、居心地の良さが生まれているのだと思います。離職率も業界の中では低いと自負していますし、これは大きな特色です。
そして、ゲームづくりの中で頭角を現してきた人材に今度はビジネス分野でも頑張ってもらう。そこでマッチした人が開発系の執行役員など幹部になり、会社全体のビジネスを広げていく。そういう流れがはっきりとしているのも特徴だと思います。
―― ご自身もそういったキャリアを歩まれてきましたか。
鯉沼 そうです。ゲーム作りからビジネスサイドへキャリアが変化していく転換期は30代前半でした。
もともとゲームが大好きで光栄に入社し、プログラマーとしてゲーム作りに没頭していましたが、30歳の時にディレクターをやってみてはどうかと話がありました。この時は正直なかなか割り切れず、かなり悩んだことを覚えています。結局、最初はプログラマー兼ディレクターという形になったのですが、次はプロデューサーにという話が出た時点でプログラミングからは完全に離れることになりました。
―― ゲーム作りが大好きだった鯉沼さんが、ビジネスサイドにキャリアの軸を移していく最後の決め手は何だったのでしょうか。
鯉沼 もともとプログラミングをやるなら業界ナンバーワンになりたいと思ってやってきました。ですが、自分より若い人の方がプログラミングの腕がいいと肌で感じる場面が増えてきていて、このまま私が居座るよりもできる人に譲る方がいいのかなと考えたりもしていました。
本音ではすごく悔しかったですけど、そういう見え方をし始めた自分に気が付きました。であるならば、自分自身も新しいところに身を置いて、そこでまたトップを目指せばいいじゃないかと切り替えた。切り替えたというか、自分を何とか納得させたというか。本当にゲーム作りが大好きだったんですよね。そんな経緯があって今に至っています。
ゲームに関わり 成功したいという芯があった
―― こうして社長になっていることを考えると、ゲーム作り以上にビジネスの才能があったということでしょうか。
鯉沼 どうでしょうか。とにかく一生懸命働いたのは事実です。私がプロデューサーになったとき、プロデューサーは1タイトルにかかりきりになるという慣例が当社にはありました。ですが、私はちょっと体が余るからと2タイトルを並行してやるようにしたのです。すると、どうやら自分はプロダクトの全体を設計して関係各所と調整をしながら進めていくビジネスプロデューサーのような立ち回りに適性があることに気が付きました。
といっても万事が順調にいったわけではなくて、ゲーム作りの現場からビジネス分野に軸を移した当初はやることなすこと初めてのことばかりで慣れるまですごく時間がかかりました。元々そんなに器用なタイプではありませんし、人付き合いもどちらかというと苦手で。でも、できるだけ社外の方との食事の席に顔を出すようにしたり、コラボレーション企画を提案したり、そうやっているうちに結果がついてきました。
新しい環境で必死に取り組めたのも、ゲームに関わりそれで何か成功したいという強い芯が根幹にあったからです。そのためにその時々置かれた立場で何をやるべきなのか。そればかり考えて行動してきただけだったと、今振り返ると感じます。
―― キャリアとしてはビジネスサイドに転じず、プログラマーであり続ける道もあったのですか。
鯉沼 もちろんありました。今でも社内でプログラマーをやっている同期もいます。かつて、プログラマーは30代で限界だという変な言説がある時代もありましたが、実際はそんなことはなくて40代、50代になって現役でプログラマーをやっている人もいます。当社においても、全員がビジネスサイドに移るわけでもなく、多様なキャリアが積めるようになっています。
―― 同世代でプログラミングを続ける人をみると羨ましくなりますか。
鯉沼 うーん、どうでしょう。それはそれで楽しいと思いますけど、私の場合はもうビジネスサイドに移ってからの方が長いですから、これはこれで(笑)。プログラミングを続けていたらきっとできなかった得難い経験もたくさんしましたし、今も充実した日々を過ごしています。