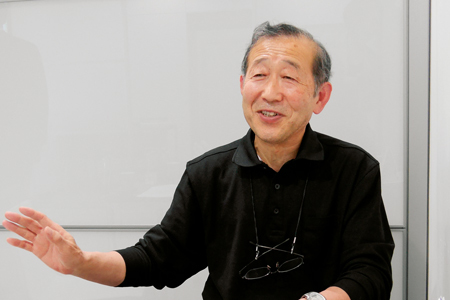江戸時代には現代のような税制はなく、江戸の町人(職人や商人)らは税金を納めなかった。だが、莫大な額に及ぶ町の運営費を負担して地域社会に貢献していた他、積極的に窮民救済を行い、「誰一人取り残さない」というSDGsの理念に近い社会を築いていた。では、そんな社会を実現していた江戸商人は、どのような理念で商売を展開していたのだろうか。文=唐島明子(『経済界』2019年8月号より転載)
地域社会に貢献していた江戸商人
江戸時代後期に導入された積立金制度
「町人らが負担した財源が、社会や治安の安定に寄与していたのは間違いない。窮民はそのお金で救済されていた」――。
江戸時代後期に老中の松平定信が導入した「七分積金(しちぶつみきん)」と呼ばれる積立金制度について、法政大学兼任講師の筑後則氏はこう説明する。
つまり日本では、江戸時代から窮民救済のための政策が実施されていたのであり、SDGsの目標「1・貧困をなくそう」「2・飢餓をゼロに」「3・すべての人に健康と福祉を」に合致する取り組みが進められていた。
七分積金の詳細は後述するが、その積立金は「町入用」という江戸時代の町の経費からねん出されていた。
町入用を負担したのは、家や土地を持つ家持町人らであり、借家住まいの店借町人らは負担することはなかった。町入用の使途は幅広く、上水道の維持管理からごみ回収、時刻を知らせる鐘撞(かねつき)、火消しの給料、神社の修繕、各種祭り、けんかの調停、囚人の管理、捨て子の養育にまで及ぶ。
町人らは積極的に地域社会の運営に参画していたわけだが、1790(寛政2)年には、その町入用の総額は江戸全体で年平均15万5千両という金額に膨れ上がっていた。
商人倫理が育まれ、不徳者には民衆の制裁
一方で、18世紀は天候不順等で農作物が不作になる飢きんに見舞われることが少なくなかった。32(享保17)年には「享保の大飢きん」、82~87(天明2~7)年には「天明の大飢きん」が発生。飢きんの翌年には米価高騰に困窮した民衆らによる「打ちこわし」が起こり、米を買い占めるなどして米価を高騰させた不徳な商人らの家や米蔵が襲われた。
そうした中、幕政改革の一環で、92(寛政4)年から七分積金の運用が始まった。幕府は膨大な額の町入用を節減させた上で、節減分の70%を町人らに積み立てさせた。実際の金額としては、15万5千両のうち3・7万両が節減され、その節減分の70%にあたる2・6万両が毎年積み立てられた。
積立金は現在の東京商工会議所の前身である半官半民の機関「江戸町会所」が運用し、飢きんに備えてもみを備蓄した他、平時には窮民への低金利融資を行った。
また積み立てに回されなかった町入用の節減分は、家持町人らの負担軽減に直結する。そこで家持町人らが、節減で楽になった分を店賃の引き下げという形で店借町人らに還元すれば、民衆の家計負担は減る。「物価が下がれば社会も安定し、治安対策にもなる」(筑後氏)
ただし家持町人らからは「節減額を少なくしてほしい」「町会所の運営に自分たちももっと参画させてほしい」等の不満の声も上がった。しかしそれでも彼らが幕府に従った理由は、七分積金で実現される窮民救済には正当性があったためだ。また窮民に手を差し伸べなければ、飢きんの後に頻発していた民衆による制裁、打ちこわしが待ち受けている。
「商人らは民衆の間でいつ悪評が出るか恐れていた。派手できれいな着物を着て表に出たら『あそこの旦那は』なんて思われてしまう。『地味にしていなければ』と商人らは必死になっていた」(同)
こうした世間の目による圧力が少なからずあっただろうが、困窮している人々に対して、自主的に施業する商人倫理の心が江戸時代の商人には育まれていたのも事実だ。
その一例が、1699(元禄12)年創業で今なお続く、かつお節の老舗・にんべんの三代目伊兵衛による「1760(宝歴10)年の大火の折、被災者救援のため無償で大量の鏡餅を配った」との行いに表れている。
さらに筑後氏によれば、江戸時代のにんべんの帳面には「深川長屋の誰それに一文あげた」というような記録が残っている。
「店に出入りしている職人が生活に困っていれば、自主的に施しをしていた。江戸の商人たちには、財産は自分だけのものではなく、世の中のものでもあるという考えがあった」(同)。
商人らは積極的に地域社会に関わり、貢献していた。
江戸商人に学ぶ持続可能社会のヒント
商売発展させ次世代に継ぐ
このような江戸時代の商人らが理想としていたのは、先代から譲り受けた商売を守り、願わくばさらに発展・繁盛させて子の世代に受け渡すこと。この考えは、SDGsの「8・働きがいも 経済成長も」にもつながる。
その理想を実現するため、商人倫理を実践する他、金銭や店の在庫を計算できる「算用」、世の中の変化に合わせて商売も適応させていく「才覚」、物事を適切に処理する「始末」を商人らは大切にした。
具体的には、算用を身に付けさせるため、子どもは寺子屋や私塾に通わせ、読み書きそろばんを勉強させる。才覚を発揮するために世の中の情勢には常に気を配り、例えば大阪で新しい商品が出て流行っているとの情報をつかんだら江戸で出す。
また、ただ無駄遣いしないだけが始末ではない。倹約する一方で必要経費は惜しまずに商売を営む。
三代目伊兵衛が残した遺言状には、「よく働いたものにはお金を出して、のれん分けをしなさいとの記載」(同)があり、まじめに一生懸命働いてくれた奉公人には、相応の援助をしていたことが分かる。
地域と共生してきた江戸商人
商人の理想の実践を心掛けた三代目伊兵衛は、二代目から引き継いだ当時は1600両だった店の資産を、約10倍の1万6500両まで増やしたという。
時が流れて江戸時代末期を迎えた日本は、1853(嘉永6)年のペリー来航に象徴されるように西洋諸国の圧力を受けて開国。西洋文化を受け入れ、第二次世界大戦後には猛烈な勢いで近代化を推し進めてきた。
そうした時代を背景に、現代には、地域社会に目を向ける余裕がない企業も少なくなかった。だが最近では、地域と共生してきた江戸時代の商人らのようにCSR(Corporate Social Responsibility、企業の社会的責任)活動に積極的な企業も増えてきている。
日本の歴史に立ち返り、江戸の商人らに学ぶことで、企業経営を発展させながら持続可能な社会を実現するためのヒントを見つけられるかもしれない。
【政治・経済】の記事一覧はこちら
経済界 電子雑誌版のご購入はこちら!
雑誌の紙面がそのままタブレットやスマートフォンで読める!
電子雑誌版は毎月25日発売です
Amazon Kindleストア
楽天kobo
honto
MAGASTORE
ebookjapan