どんな経営者も、起業から成長に至る過程で多くの困難に直面する。日本を代表する名経営者も例外ではない。時には時局に振り回され、時にはプライドを傷つけられながらも、状況を打開し、そのたびに経営者として成長していった。危機に際して彼らは何を考え、どう行動したのか。文=流通科学大学特任教授/長田貴仁(『経済界』2021年5月号より加筆・転載)
従業員を尊重した経営者
元祖CSR型経営者の大原孫三郎
経営者は公私のうち「公」、つまり企業経営の部分が注目される。当然のことだが、「私」において直面した逆境が起因となり自己変革し、経営史に残る偉人になった事例も少なくない。
例えば、大原孫三郎(現・クラボウ、クラレ、中国銀行、中国電力元社長)である。孫三郎の孫である大原謙一郎(クラレ元副社長、中国銀行元副頭取)によると「孫三郎は東京専門学校(現・早稲田大学)時代に、今の額で言えば1億円以上の借金をして豪遊し、倉敷に呼び戻された」という。
その後、キリスト教に触れ回心する。従業員を大切にし、社会に貢献することを最大目的とする経営姿勢を貫いた。元祖CSR重視型経営者と言えよう。

出光佐三の教えは「逆境において楽観せよ」
従業員を尊重したという点では、出光佐三(出光興産創業者)は特筆すべき経営者である。出光は、1945年8月15日の敗戦により、ほぼすべての事業と在外資産を失った。しかし、すぐに「愚痴をやめて再建にとりかかろう」と従業員に呼び掛け、海外から引き揚げてくる従業員を一人たりとも首切りしない、と宣言した。
このような逆境に耐えられる姿勢を貫けたのも、「順境にいて悲観せよ」(景気の良い時に、悪い時のことを考えて準備しておけ)、「逆境において楽観せよ」(逆境の時立てた計画は堅実で間違いない)といった攻守の妙を駆使したからである。

豊田喜一郎の精神を受け継ぐ豊田章男
豊田喜一郎(トヨタ自動車創業者)も、「上下一致し家族的美風とすべし」という父・佐吉(豊田自動織機創業者)の経営理念を受け継いでいた。が、時代の逆風に逆らうことはできなかった。
49年10月から実施された自由販売への移行により、月賦手形による分割払いが増加した。平均月賦期間が長期化する傾向が顕著になり、不渡り手形の大量発生につながった。その穴埋めを迫られたトヨタ(自動車工業)は深刻な経営危機に陥った。喜一郎は不本意ながら1600人の希望退職者を募集せざるを得なくなり、労働争議が激化した。喜一郎はこの責任をとるため辞任したのだった。
2018年8月6日、愛知県豊田市のトヨタ自動車本社において、創業者である豊田喜一郎の米国自動車殿堂入りを記念した式典が開催された。その際、現社長で孫でもある豊田章男は次のようにスピーチした。
「喜一郎は『自動車づくりは、みんなでやったんだ』との想いを強く持っていました。だから祖父であれば、『自動車殿堂にも、みんなで入るのだ。自分は代表して名前があるだけだ』。必ずそう言ったはずです」
豊田喜一郎が逆境を乗り切るために断行した人員削減の悔しさは、孫にも受け継がれているようだ。二度と手をつけてはいけない、と。
幼少期の逆境を原動力とした経営者
「日本のエジソン」と呼ばれた早川徳次
豊田喜一郎と同世代ながら、御曹司とは異なり幼少期における逆境が後の企業家活動の駆動力になった経営者もいる。その代表格が早川徳次(シャープ創業者)と松下幸之助(パナソニック創業者)だろう。
早川徳次は、継母から虐待を受け続けていた。それを近所の人たちが見かねて、錺屋(金属加工業)の店へ連れて行き奉公させたのだった。早川は懸命に働き、1912年9月に独立した。そのきっかけになったのは、初めて特許を取得した「徳尾錠」(バックル)である。
さらに、社名の由来にもなった「シャープ・ペンシル」を世に送り出した。日米で大ヒットしたが、23年9月1日、30歳の早川に再び不幸が襲う。関東大震災である。妻と2人の子どもを亡くし、工場も焼失してしまった。残ったのは多額の借金だけ。
幸い、大阪企業の社長から「技術指導をしてもらえませんか」と声が掛かった。半年間、働いて貯めた資金を元手に、24年に大阪・西田辺にシャープ(旧・早川電機工業)の前身となる早川金属工業研究所を創業し、国産初のラジオを開発し販売を開始した。早川を逆境から救ったのは、「日本のエジソン」と言われた名声と実績であった。
松下幸之助の名言「逆境は尊い試練」
一方、生家が破産し9歳にして丁稚奉公に出た松下は、18年に23歳で松下電気器具製作所を創業してから2度の倒産危機に瀕した。まずは、29年の世界大恐慌下での販売急減。続いて第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)から財閥と見なされ、会社解体を余儀なくされた。
松下は逆境を乗り越えられた要因として「素直な心」と「人とのつながり」をあげている。「素直な心」とは苦しい、つまらないと感じることでも、逃げることなく、真正面から取り組めば、道は開けると思う心掛けを意味している。「人とのつながり」には名番頭だった高橋荒太郎や、後に三洋電機を創業する井植歳男(と祐郎、薫の「井植三(義)兄弟」)たちの献身的な協力も含まれる。
松下は、著書『道をひらく』で「逆境――それはその人に与えられた尊い試練であり、この境涯にきたえられてきた人はまことに強靭である」と述べている。

グローバルブランドを育てた経営者
ホンダの成長をもたらした本田宗一郎の「やらまいか精神」
第二次世界大戦直後に「焼け跡派ベンチャー」としてスタートし、日本を代表するグローバル・ブランドに成長した企業と言えばホンダ(本田技研工業)とソニーである。
ホンダの創業者である本田宗一郎には、浜松の「やらまいか(やってみよう)精神」が息づいていた。その心意気は、ホンダの独自性を育んでいくが、方や、逆境と背中合わせでもあった。
本田技術研究所として起業してから9年目の55年、浜松では54年時点で二輪車メーカーが200社を超えていたが、翌年には137社が撤退するという多産多死現象がみられた。ホンダも多死の1社と見られていたのだった。
それもそのはず。同社は53年に、4億円という巨額を投じて最新の欧米製工作機械を購入したからだ。大卒の初任給が約1万円という時代である。身の程知らずの暴挙と見られていた。ホンダ倒産説に対して、本田は「会社はつぶれるかもしれないが、機械そのものは日本に残る。それは必ず日本の産業界に役立つはずだ」と反論した。
幸い58年、最新鋭工作機械を活用して量産しリーズナブルな価格にした二輪車「スーパーカブ」が大ヒットし、会社がつぶれるどころか急成長をもたらした。
本田は次の言葉を遺している。
「自分がいろんなことを率先して試みているから、社員も安心して新しいことがやれる。だから試すことは本当に大事なのです」
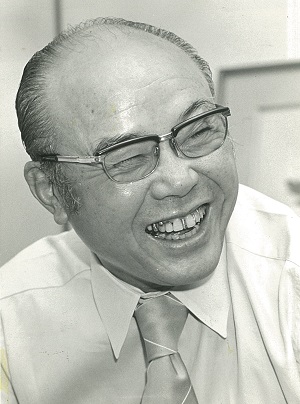
ソニーを育てた「武士は食わねど高楊枝」
ソニー(旧・東京通信工業)を創業した盛田昭夫にとっての逆境を乗り越えるパワーの源泉は、「武士は食わねど高楊枝」と言えるプライドだった。このことを物語るエピソードがある。
55年、アメリカの大手時計会社のブローバー社から、日本初のトランジスタラジオ「TR-52」に10万台という大量注文が来た。この朗報を耳にした日本のスタッフは大喜びした。だが、盛田は「ノー・サンキュー」と断る。その理由は、ブローバー社のブランドを付けて売るOEMの発注であったからだ。
「誰が、ソニーなんか知っているんだ。当社は、50年かかり、世界中に知られるブランドにしたんだ」
こう言ったブローバー社の責任者に盛田が切った啖呵は、ブランドを考える上で大いに参考になる。
「それでは、50年前、何人の人が、あなたの会社の名前を知っていたのでしょうか。わが社は、50年前のあなた方と同様に、今、50年の第一歩を踏み出したところだ。50年たったら、あなたの会社と同じくらいにソニーを有名にしてみせる」
盛田はおいしい大商談を逃してしまうことを逆境と考えなかった。このうまい話に乗ることこそ、ソニーブランドの首を絞める要因になると確信したのである。「うまい話には裏がある」とはよく言ったものである。

心の持ち方を軸とした経営者
「感謝の心」を説く稲盛和夫
京セラ(旧・京都セラミック)を創業した稲盛和夫が歩んできた89年間は「逆境と向き合う人生」だった。稲盛は、戦時下の空襲で家を焼失した上に不治の病とされた結核を患い中学受験を二度失敗。大学受験や入社試験も希望通りにはいかなかった。やっと就職した京都の松風工業では、給料の遅配が続く倒産寸前の状態だった。そのことに不平不満を持ち、何度も会社を辞めようと思ったが、「心の持ち方」を変え研究に邁進した。
捨て身の努力が実を結び、ファインセラミックスの製品化に成功した。これが、京都セラミックという会社を起業するきっかけとになった。この頃、手を差し伸べてくれる人に出会ったことから、稲盛は「感謝の思い」を強く抱くようになると同時に、「自分はなんと幸せなんだろう」と思えるようになった。
人々に支えられることによりできた会社を潰してはならない、従業員を路頭に迷わせてはならない、と稲盛は考えた。そして、生きているのではなく、生かされている。感謝の心が生まれてくれば、次には幸せが感じられるようになると信じた。今も稲盛は、逆境のときこそ試練に感謝し、今まで以上に努力を重ねることが大切であると説いている。

従業員の不祥事を契機に不屈の精神を培った飯田亮
稲盛が第二電電(現KDDI)を創業する際、規制緩和のために闘った「戦友」の飯田亮(セコム創業者)にとっての逆境は、改革のチャンスである。
飯田は、従業員を前にしてこう述べている。
「物事に行き詰まり、前に進まなくなると、『しょうがない』という言葉を使って、妥協してしまうことがよく行われている。考え抜いて精魂尽き果ててから、もう5分多く考えて、なぜ打開する道を探らないのだろうか」
飯田には、この言葉を裏付ける痛い経験があった。
「警備先の伊勢丹で宝石類600万円相当を盗んだ容疑で、うちの社員が2人逮捕されました」
66年9月29日夜、三重県四日市市へ出張していた飯田に会社から電話がかかってきた。翌朝、急遽、東京へ戻り、伊勢丹の取締役庶務部長だった前川篤二郎にお詫びをして許してもらった。ところが、その事件だけではなかった。66年11月上旬までの1カ月間で、社員による窃盗事件が5、6件続けて起きた。
「バカ野郎。警備している奴が泥棒をするとは何事だ」
顧客企業の総務担当者から、本を顔に投げつけられた。
「本当に申し訳ございません」
飯田は平身低頭謝った。その会社から表へ出ると屈辱感で涙が溢れた。
急成長会社としてもてはやされていただけに、マスコミが連日報道した。「またガードマンが泥棒」という新聞の大きな見出しを見て、飯田は、倒産するかもしれないと思った。それは当然だろう。警備会社が窃盗、では冗談にもならない。致命的過失だ。
そこで、飯田はテレビで1分間謝罪し信頼回復を誓った。この事件を契機に、飯田は従業員と対話するため、全国の拠点を行脚した。こうして創業者自らが現場に赴き発信することで、社内の結束力はより一層強まった。

自ら逆境に身を置いてきた経営者
「小売りの民主化運動」に身をささげた中内功
最後の事例として、逆境を乗り切れなかったと見られている中内功(ダイエー創業者)を取り上げたい。
中内はスーパーマーケット(GMS)という業態を日本で最初に実現し、72年には売上高で三越を抜く。「流通革命の旗手」は日本の「流通王」に上り詰めた。ダイエーは80年には日本の小売業でははじめて売上高1兆円を達成したが、バブルの崩壊、阪神・淡路大震災の煽りを受け、経営不振に追い込まれ、2015年1月よりイオングループの一員(完全子会社)となった。それまでも、中内は、度々逆境に直面し、闘い続けてきた。その相手は「既成事実」を変えようとしない「権威」であった。
1942年、旧制・神戸高等商業学校(現・兵庫県立大学)を卒業した中内は、商社の日本綿花(現・双日)に就職するも翌年1月に出征した。広島の訓練所から満州を経て、44年7月にフィリピン・ルソン島リンガエン湾へ。戦闘で敵の手榴弾を被爆し死を覚悟した。玉砕命令が下されたが、終戦を迎え辛うじて生き延びた。まさに、大岡昇平の戦記小説『野火』に描かれたような地獄を見たのだった。逆境中の逆境と言える原体験である。
中内は終戦後、焼け跡となった神戸・元町の国鉄(現JR)高架下で薬局を営みながら、旧制・神戸経済大学(現・神戸大学)の夜間に通った。晩年、同学の教授から「あの頃、どの科目が一番面白かったですか」と聞かれると「(先生方には)悪いがどれも面白くなかった。唯一、日本国憲法の講義は役に立った」と語っていた。軍国主義に翻弄された中内は、民主主義と自由に興味を持ったのだろう。
「価格の決定権をメーカーから消費者に取り返す」という信念のもと、64年から30年にわたり、松下電器産業(現パナソニック)との間で起きた商品価格の値下げに端を発した対立は、「よい品をどんどん安く より豊かな社会を」と訴えた中内にとって「小売りの民主化運動」であったとも解釈できる。
83歳でこの世を去った中内は、2022年に生誕100年を迎える。自ら逆境に身を置き闘い続けてきた「革命家」は、逆境を回避するのは上手だが、闘わなくなった昨今の経営者を天国からどのように見ているだろうか。(敬称略)





