インタビュー
新型コロナウイルス流行から1年もたたずに実用化されたコロナワクチン。この驚異のスピードは、創薬ベンチャーだからこそ実現できた、と言うのは同じく創薬ベンチャー、窪田製薬ホールディングスの窪田良社長。窪田氏は元眼科医。なぜ医学の道から起業家へと転じたのか。聞き手=関 慎夫 Photo=横溝 敦(『経済界』2021年6月号より加筆・転載)
窪田 良・窪田製薬ホールディングス社長プロフィール
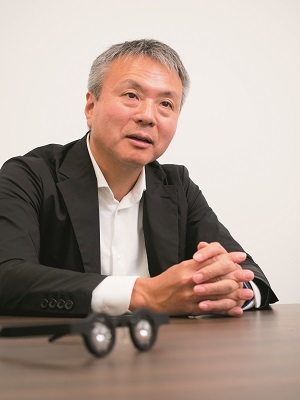
クボタメガネで近視は治療できる
―― かけるだけで近視を矯正できるかもしれない「クボタメガネ」が話題を呼んでいます。どういう仕組みですか。
窪田 まず、なぜ近視になるかというと、近視の多くが「軸性近視」です。網膜が本来あるべきところより後ろに伸びてしまい(軸長が伸びる)、ピントが合わなくなってしまっています。なぜそうなるかというと遺伝要因と環境要因がありますが、環境要因はスマホやパソコンなど、近くのものを長時間見ることで起こります。
クボタメガネはLEDライトを使って、網膜より前に焦点を結びます。いわば疑似的に遠くを見ているように錯覚させるのです。これを続けることで、近視になる時とは逆に、軸長を短くなることが実験で確認されています。
これは理論としては以前から分かっていましたが、一度伸びた身長が縮まらないように、一度伸びた軸長を短くするのは難しいと思われていました。でも実験では短期的には軸長が短かくなることが分かりました。ですから成長が止まった大人の近視を治すのは難しいかもしれませんが、近視が起こり始める5、6歳から10代にかけて使用すれば治療できる可能性があります。
―― 窪田さんはもともと慶應大学出身の眼科医でした、世界から失明患者をなくしたいと考え、アメリカで創薬ベンチャーを立ち上げています。近視治療というのは、これまでと路線が違うのではないですか。
窪田 そうではありません。白内障や緑内障、あるいは黄斑変性など、年を取るとさまざまな目の病気が起きてきますが、近視はそのリスクファクターです。長年近視のままでいると、さまざまな負担が目にかかる。それが失明に至る病気につながります。
ですから近視を治療することで失明を減らすことができます。脳梗塞や心筋梗塞を起こしてから治すのは大変です。そこでリスクファクターである高血圧を是正する。それと同じような考え方です。
―― いつ頃商品化できそうですか。
窪田 医療器具ですから、国の認可を取らなければなりません。国によって必要なデータを取る期間も違いますが、早いところで年内にも認可が得られることを期待しています。その国でまずテスト販売をして、徐々に認可を増やしていこうと考えています。ただし、今まで世の中に全く存在しなかったデバイスですから前例がありません。ですから実際いつ認可されるかははっきりしていません。

宇宙で使える眼科用機器をNASAと共同開発
―― 窪田製薬は宇宙で使える眼科用機器をNASAと共同開発しています。前12月期に窪田製薬は4期ぶりに売り上げを上げましたが、それはNASAの開発受託金を売り上げとして計上したものです。今後、どう進んでいきますか。
窪田 長期間、宇宙に滞在した宇宙飛行士の多くが、視神経が腫れるなどの眼疾患にかかっています。放置すると失明につながる危険性もあるので、早めの診断が必要です。そこで宇宙船に搭載できる超小型の診断装置を共同開発しています。
ただし、バイデン政権が誕生したことで、少し風向きが変わりました。トランプ前大統領は宇宙開発に熱心で、2030年代に火星に人類を送ることを目指し、NASAにも多くの予算を回しました。
ところがバイデン大統領は、宇宙のことより、温暖化対策など地球環境をよくすることに力を注いでいます。前大統領のやってきたことの逆をやっていますし、NASAのスタッフも大きく入れ替わりましたから、今はどうなるか分からないという状況です。
チャンスに打席に立てることがモチベーションに
―― 新しい薬ができるのは3万分の1の確率と言われます。窪田製薬でも以前、加齢性黄斑変性の特効薬と期待されたパイプラインが、最後の第3相試験で認可されなかった過去があります。そのため、一時、6千円以上になった株価が暴落、現在も200円台です。しかも、今の話のように、政府の方針ひとつで事業化できるかどうかが決まることもある。あまりにもリスキーです。
窪田 創薬ベンチャーとはそういうものです。今われわれは、スターガルト病という網膜の遺伝性疾患の治療薬候補「エミクススタト塩酸塩」の第3相試験を行っています。またクボタメガネなどのデバイスや眼疾患の遺伝子治療にも取り組んでいます。
エミクススタトは臨床試験が来年終わりますので、これが会社の命運を決めるでしょうね。あるいはクボタメガネが認可を得て発売できるか、それとも他の取り組みに対して何らかの形でファンディングがつくかによって、会社が存続するかどうかが決まります。でも振り返ってみれば、創業から約20年、今までよく続いたな、というのが正直なところです。
―― 気の休まる時もないでしょう。何が窪田さんのモチベーションになっているのですか。
窪田 チャンスに打席に立てている。これがうれしい。高校球児が甲子園に出場し、打席に立って投手と勝負できれば、それだけでうれしいのと一緒です。結果は空振りすることもあればホームランを打つこともある。
僕の場合、今のところ空振りばかりですが、投資家のお金、パートナーのお金や、各国政府からいただく補助金が、僕を打席に立たせ続けてくれています。誰かがクレージーなリスクを取らないと新しいものは生まれてきません。僕はそれを託されているのだからとてもありがたいと思っています。
もちろん創薬ベンチャーで成功する確率が恐ろしく低いことも分かっています。だからこそ、うまくいかないのが当たり前。それを20年も続けてこれたのだから、楽しいというか面白いというか。20年前も今も、世界を変えるかもしれないプロジェクトに関わることができるのは、想像を絶する喜びです。そういうチャンスを与えられているというのは、ワクワクドキドキしかありません。
―― 眼科医を続けていたのでは、味わえない喜びですね。
窪田 目の前の患者さんが、病気が治って喜んでくれる。これはこれでものすごい喜びです。患者さんに会うと、みなさん感謝の言葉を口にしてくれる。半径10メートルの人たちにいつも感謝される仕事というのは非常にやりがいがありました。
でも僕は、日本人のプレゼンスを世界に示して、日本人は物真似だけではない、世界になくてはならない重要な国だと思われたいという根源的な願望があります。
ほとんどの人は、毎日おいしいご飯を食べて暮らせて、平和で治安がよければそれでいいと思うかもしれません。でもそれを維持できるのは、先人の方々が努力をされて、外貨を稼ぐ産業をつくりあげてくれたからです。そのお陰での豊かさであり平和です。でも何もしないでいたら維持することはできません。そのために微力ながらやれることはやりたいというのが、僕の生きがいというか趣味になっています。
米国流ベンチャーを応援するエコシステム
―― 大企業のような組織の中でそうした願望を実現することは難しいのですか。
窪田 無理ですね。新型コロナウイルスのワクチンを開発したモデルナもビオンテックもベンチャーです。小さな会社ですが、スピードとアイデアがありリスクテイクができる。そこにラッキーが重なれば、世界を変えることができる。それをコロナのmRNAワクチンが証明しました。
僕らもそうですが、ベンチャー企業はみな、明日つぶれるかもしれないというプレッシャーの中で戦っています。大企業が社員に対して好き勝手やっていいよと言ったところで、全く違います。すべて失うかもしれないというプレッシャーがあるかどうかが非常に重要です。
―― ですから日本人は起業に対して及び腰になってしまいます。
窪田 アメリカはベンチャーエコシステムが出来上がっています。会社がつぶれたからといって人間が死ぬわけではありません。しかも再チャレンジの機会も与えられる。だからこそイノベーションが起こってくる。ハーバード大学の卒業生は半分以上が起業します。しかも優秀な人ほど、世界を変えるために起業する。そしてその人たちを応援する社会です。
日本でもプロ野球選手になりたいという子どもがいたら、夢が叶う確率はとんでもなく低いけれど、応援するでしょう。アメリカ人は起業を志す人を同じように応援します。誰もがイーロン・マスクやジェフ・ベソスになれるわけではないですが、目指しているなら応援する。
常に変化する方が結果的に安定する
―― 親は子どもに安定を求めないんですか。
窪田 むしろ起業するなど夢を追いかけたほうが安定するという考えです。生命生物的に言うとダイナミックスタビリティ(動的安定性)で、常に変化するほうが結果的に安定する。あるいは自転車のように、走り続けるから立っていられる。それにチャレンジして失敗しても、その経験がある人のほうが、企業にとっても価値があるので就職先に困らない。ある意味非常に合理的です。
僕だって、日本にいたら起業はしなかったと思います。アメリカだから起業できた。なので僕は若い人に、どんどん海外に出てこの空気感を味わってほしい。失敗してもチャレンジしたほうがベターな選択肢が広がるなら、誰もがチャレンジします。
しかも一度味わうと、やめられなくなる。これは恐らくスカイダイビングを飛び続けている人と一緒です。もしかしたら地上に叩きつけられて死ぬかもしれない。でも飛び続けるのはアドレナリンが出てワクワクするから。僕も20年間、そのワクワクを味わい続けています。
