過去2年程度を振り返ると、賃上げが話題になることが増えてきた。政府・日銀も物価と賃金の好循環を最重要の政策目標として掲げ、来る春闘の先行きに対し固唾を飲んで見守っている状況だ。本稿では賃上げの持続可能性について論じることとする。(雑誌『経済界』巻頭特集「『安いニッポン』さようなら~日本の給料を考える~」2024年4月号より)
鶴 光太郎 慶應義塾大学大学院商学研究科教授のプロフィール
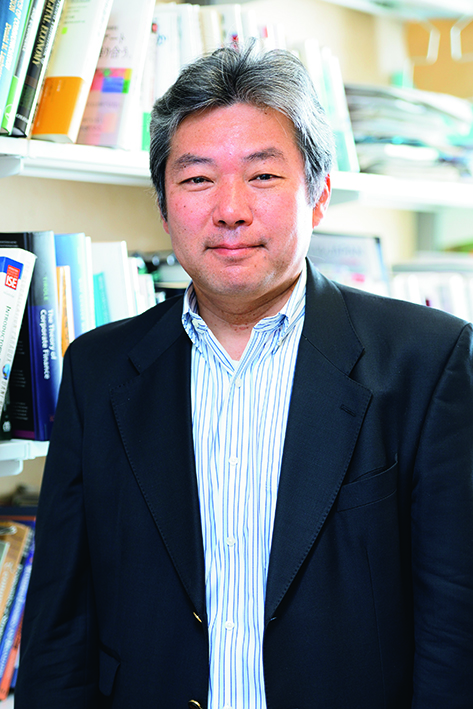
つる・こうたろう 1960年東京生まれ。84年東京大学理学部数学科卒業。オックスフォード大学 D.Phil. (経済学博士)。経済企画庁調査局内国調査第一課課長補佐、OECD経済局エコノミスト、日本銀行金融研究所研究員、経済産業研究所上席研究員を経て、2012年より現職。経済産業研究所プログラムディレクターを兼務。内閣府規制改革会議委員(雇用ワーキンググループ座長)(13~16年)などを歴任。主な著書に、『人材覚醒経済』(日本経済新聞出版)、『日本の会社のための人事の経済学』(日本経済新聞出版)などがある。
ウクライナ侵攻以降の資源価格高騰が後押し
賃上げが注目を集めているのは、2022年のロシアのウクライナ侵攻を契機にエネルギー・食糧などの資源価格が高騰し、輸入物価を通じた海外要因により、消費者物価の前年比が2~4%となるなど何十年ぶりかの高い伸びを示すようになり、物価高の時代になったことが背景だ。物価が上がるのに賃金が上がらなければ、生活水準を決める実質賃金は当然のことながら低下してしまう。
このため、23年の春闘賃上げ率は、3・6%とこうした物価高を背景に30年ぶりの高い賃上げ率となった。24年についても、昨年を上回る賃上げを表明する企業も出てきており、連合も目標として5%以上の賃上げを掲げている。長期のデフレの中で国民に浸透してきた「物価や賃金は上がらない」というノルム(社会規範)に転換の兆しがみえ、物価上昇を上回る賃金の上昇が実現することが、デフレからの完全脱却という政府の目標実現や日銀の物価目標2%の確実な達成につながることが期待されている。
ここで、賃上げを評価する際に重要な点として認識しておくべきことは、春闘賃上げ率は、企業に勤続すれば毎年自動的に上がる定期昇給の部分とベースアップ部分からなることだ。注意すべきは、経済全体の賃金上昇、ひいては物価上昇を決めるのはベアの部分であることだ。定昇は企業の中の勤続年数と賃金との関係を示す賃金カーブを決定し、年功賃金の重要な要素となっている。しかし、定昇があってもそれが毎年同じ率であれば、人員構成などに変化がない限り企業の賃金支払い総額は変わらない。高賃金のシニアが定年で退職し、低賃金の新卒と入れ替わるからだ。この場合、マクロ経済全体で集計された賃金指標も変化しないことになる。
したがって、定昇の部分は毎年の企業の追加的な負担にはならず、賃上げが「かさ上げ」されているといっても過言ではないのだ。賃上げを物価上昇につなげるという意味では、ベアの部分に着目するべきである。その意味で、過去20年ほどの間、ほとんど実施されなかったベアが昨年、2%程度達成されたことは画期的といえる。24年の春闘ではベア部分が昨年を超える3%程度になるかが注目を集めているところだ。
しかし、こうしたベアの持続的な伸び率が来年以降も継続するかどうかは予断を許さない状況である。なぜなら、そもそも、1990年代以降の大きな環境変化に抜本的に対応するために、特に、大企業・メンバーシップ型企業の労使は、90年代末から2000年代初頭にかけて、中高年の正社員の雇用維持を引き換えに、新卒採用抑制・非正規雇用の増大、ベア抑制容認に舵を切ったと筆者はみているからだ。労働組合は企業の追加的な負担になるベアは雇用保護と引き換えにあきらめたといっても過言ではなく、こうした基本的な構図が変わったわけではない。消費者物価上昇率も昨年初をピークに鈍化傾向にあり、輸入物価の影響は弱まってきている。物価上昇が一時的なショックと認識されれば、ベア抑制の根本的背景が変わっていない以上、賃上げ機運は短命に終わる可能性は否定できないのだ。
物価上昇と賃金増加の関係性を再考する必要性
また、マクロ経済全体の観点からは、物価が上昇している時に賃金を上げるべきかどうか必ずしも自明なことではない。「労働分配率を変えないような実質賃金の上昇」という考え方に沿って説明してみよう。この考え方によれば、労働分配率を変えないような賃上げを実施するには、労働生産性に見合った実質賃金の上昇を図る、輸入インフレで交易条件が悪化する場合は、海外への実質所得の流出が起こっているとみなされるので、それに見合った実質賃金の低下を受け入れるというものだ。
1970年代の教訓は、海外要因でインフレが起きた時は実質賃金低下を受け入れ、労働分配率の過度な高まりを抑えるというものであった。その意味では、現在の状況も70年代とは変わらない。海外要因で物価が上昇している場合は、むしろ、実質賃金の低下を甘受すべきであるはずなのだ。そこで無理に賃上げを実施すれば、労働分配率は急上昇し、企業の設備投資減につながるなど経済への副作用は覚悟しなければならない。
加えて、大企業のいくつかが前年を上回るベアを表明してもその動きを中小企業に広めていくのは至難の業だ。なぜなら、中小企業のコストの価格転嫁力は大企業に比べても弱いためだ。ある研究によれば、日本企業の価格転嫁力(コストにマージンを乗せて価格設定する力=価格マークアップ率)は2000年代に入って明確に低下し、特に、非製造業・中小企業はそのレベル、低下幅が大きいことを見出している。これは、非製造業・中小企業の方が競争環境は厳しく、価格転嫁がより難しくなってきていることも意味している。また、この研究はそういう傾向が強い企業ほど、賃金抑制を強め、労働分配率を一定に保つ傾向があることも示している。つまり、非製造業・中小企業は価格転嫁が難しいから賃上げも難しくなっているのだ。
こうみてくると、物価が上がれば賃上げすれば良いという単純な問題ではないことが分かる。そもそも、物価と賃金の好循環は国民にとって必要なのか。物価が上がって、賃金がそれ以上になったとしても、さらに物価が上がってしまえば、実質賃金は上がったことにはならない。物価と賃金の好循環が継続しても実質賃金が上がる、つまり、生活水準が向上する保証はどこにもないのだ。00年代以降、マクロで見た物価と賃金は上がらなかった。しかし、大企業を中心としたメンバーシップ型企業では定昇がある分、従業員は毎年賃金が上がるため、それほど困ったわけではなかったことも留意すべきであるし、正社員の雇用維持を最優先するメンバーシップ型雇用がベア抑制の要因になってきたともいえる。
それではどうすれば良いのか。目指すべき政策目標は物価と賃金の好循環ではないことは明らかだ。そうではなく、実質賃金の持続的上昇である。それは、労働分配率を変えない賃金上昇のフレームワークでも明らかである。実質賃金の上昇のために労使が自分たちでできることは、一人当たりの従業員の生み出す実質的な付加価値(=労働生産性)を高めるしか道はないのだ。他社と同じような財・サービスで競争すれば、徹底した価格競争になり、付加価値、マージンを上乗せすることは難しくなる。他社とは異なる財・サービスを提供するという製品差別化戦略が重要となり、特に、非製造業・中小企業の喫緊の課題であろう。実質賃金の持続的上昇を達成していくためには、メンバーシップ型雇用およびそれと強固に結び付いてきた横並び同質的な企業戦略の見直しが求められる。



