吉本興業会長を退任し、大阪・関西万博催事検討会議の共同座長に就任した大﨑洋氏。幅広い人脈をフル活用して、開会式および閉会式、一般イベントのほか、各種祭典行事の準備を先頭に立って進めてきた。そんな大﨑氏に、今の時代における万博の意義と、大阪・関西で開催する万博に込める思いを聞いた。聞き手= 武井保之 Photo=山内信也(雑誌『経済界』2025年3月号「万博の夢と希望を、もう一度!」特集より)
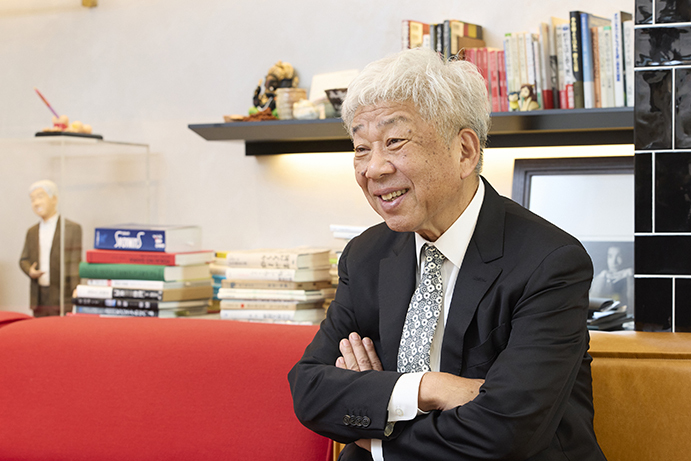
おおさき・ひろし 1953年、大阪府生まれ。78年吉本興業入社。2009年社長、18年共同代表CEO、19年会長に就任。23年6月に退任し、大阪・関西万博催事検討会議の共同座長に就任。内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局「わくわく地方生活実現会議」委員、「2025年日本国際博覧会協会」シニアアドバイザー、近畿大学客員教授などを歴任する。
55年前は世界が日本に来た万博。今回は日本から世界に発信する
―― 55年ぶりの大阪での万博開催になります。1970年の大阪万博をどう覚えていますか。
大﨑 当時、高校2年生でしたが、日本が戦後から立ち直って先進国の仲間入りをし、高度経済成長のピークくらいの頃です。世界に向けて、日本はこんなに立派になりました、どうぞお越しくださいという、人類の進歩と調和をテーマにした万博だったと記憶しています。
僕は高校の遠足で来て「太陽の塔って変な形やなあ、月の石を見るのになんで何時間も並ぶんかい、動く歩道ってふつうに歩けばいいやん、人間洗濯機って体くらい自分で洗うわ」とか言って斜に構えていましたね(笑)。でも、今71歳になって、動く歩道にとても助かっています。病院や老人ケア施設の入浴設備は世の中の役に立っています。当初、気味が悪いとも言われた万博キャラクターのミャクミャクは子どもたちに人気になって、当時の太陽の塔のような万博の象徴になっています。50年後に大阪で万博が開催されることになって、当時のいろいろなものの意味がやっと分かった気がします。
その頃の中高生なんて、外国人に会ったこともない時代だから、サイン帳を片手に、外国人を見たらサインしてもらう(笑)。その数を競ったりしていました。そこから世界にはいろいろな人種がいて、異なる文字や言葉などの文化があることを知り、興味を持っていく。さまざまな国のパビリオンを周って外国人と触れあうことで、世界で仕事をしたいという夢を持った子どもたちも多かったと思います。
―― そんな万博を経て、日本が成熟しきった社会になった今万博を開催する意義はどう考えますか。
大﨑 70年の万博から55年を経た今回は、日本から世界に何かを伝える万博になるでしょう。それは科学や芸術、歴史といった文化だけでなく、アニメや漫画、ゲームといったポップカルチャーもあるかもしれない。一方、毎年のように起こる大規模な自然災害や、少子高齢化による超高齢社会といった社会課題も多くあります。それは日本に限らず、先進国に共通する課題でもありますし、地球をあっという間に何周も回る感染病などの世界的な課題もあります。2025年は、社会課題先進国である日本から、あらゆる社会課題を発信し、世界の英知を集める万博になるでしょう。
もちろん課題を解決することは大事ですが、それ以上に重要なのは、まず問いを立てること。それに対して、世界の子どもや若者たちがそれぞれ答えを見つけていく。後に振り返れば、世界中が力を合わせて社会課題の解決に向かうスタートになったのが、25年の大阪・関西万博になる。そんな意義があると思っています。メディアではいろいろ叩かれたりしていますけど(笑)。
大阪・関西万博参画のために吉本興業会長を退任した真意
―― 今回の万博に向けては、23年6月に吉本興業の会長を退任し、万博催事検討会議の共同座長に就任されました。
大﨑 万博イベントなど祭典の企画運営の依頼を経済産業省から受けていました。当初、東京オリンピックのあと携わった人たちの問題を見ていたので辞退しましたが、催事のための民間組織をつくるので、華道池坊・次期家元の池坊専好さんと2人で座長を務めてほしいとオファーがあり、それならと引き受けました。
僕は大阪生まれの大阪育ち。吉本興業も大阪で成長していった会社です。今の僕が大阪にできる恩返しをしたい気持ちが強くありました。大阪・関西が元気になれば、日本中に伝播する。国政は東京中心になりますが、経済と文化は東京と大阪・関西の二極あったほうが、日本が良くなる。地方の経済や文化の活性化につながるチャンスだと思ったので、吉本興業を辞めてそちらに専念しようと決めました。
岡本(昭彦)社長に「吉本辞めるわ」って話したら、「えー、何言ってるんですか」って驚かれましたけど(笑)。ただ、その前から僕がいつまでも吉本興業にいるのもどうかと思っていたんです。社長を退いて会長になってからも、院政になっただけとかメディアに言われたりして。会社や岡本社長に迷惑をかけてもいけないので、辞めるタイミングを考えていたところだったから、ここでスパッと踏み切りました。
―― 大﨑さんは、大阪の一企業だった吉本興業を、日本を代表するエンターテインメント会社に成長させ、関西のお笑いを日本の近代芸能文化のひとつとして確立させた立役者です。その吉本興業ではなく、万博催事検討会議の共同座長として、大阪で開催される万博に関わることに抱く感情はありませんか。
大﨑 大阪・関西には、言葉のイントネーションやリズムをはじめ、日常の生活の中に笑いがあふれる街の文化があります。そんな笑いが絶えない文化を、大阪を中心に世界に発信したいという思いだけです。日本はこれから緩やかに坂道を下っていく。そこにあるいろいろな課題を解決しないといけない。それには、高度経済成長期の倍以上の時間がかかるかもしれない。だからこそ、笑いながら楽しんで解決していくのがいい。
吉本興業では、会長になってから、そもそも自分は何をやりたかったのかをずっと考えていました。もともと僕はお笑いが特別に好きでこの会社に入ったわけではなくて、ただ仕事が楽そうで、楽しそうだったから。この仕事以外に、自分の人生でやれたかもしれないことをいくら考えても、何も思いつかない。でも、70歳を過ぎて、今もがいたら、何かを見つけるかもしれないと思った。それを万博催事検討会議の仕事の中でやればいいかもしれないし、そうじゃないかもしれない。ただ、万博が掲げる社会課題の提示にヒントがある気がします。そこから何かを得られれば、万博が終わった後にその活動を続けることができたらいいなと思っています。
ネガティブな論調が目立つメディアへの違和感
―― 開幕まで3カ月ほどに迫りました。世の中の機運をどう感じていますか。
大﨑 万博協会や関係者のみなさんが認知拡大や機運醸成に一生懸命取り組んでいますが、専門外のマーケティングやプロモーションで苦戦している感はあります。協会と自治体の考え方や立場の違いがあって困難なことも多いのですが、少しずつ着実に前に進んでいます。
―― メディアでは膨らみ続ける予算に対するネガティブな論調も目立ちます。
大﨑 課題は山積みですけど、それを認識した上でどう解決していくかという方向に報道が向かないのが残念です。叩くだけ叩いて、フォローも代案も出さない。売れるからという理由の情報の切り取りを見ると、マスメディアの役割を果たしているのか、と疑問に思うことはあります。
―― 大﨑さんが万博に期待することを教えてください。
大﨑 これからの世の中は、地球上のみんながお祭りの神輿を一緒に担ぐように、助け合って生きていかないといけない。世界中の言葉も文化も、習慣も価値観も国民性も異なる人たちが、お互いの共通点を見いだしたり、心のどこかで共感を得てもらえる万博にしたいですね。
催事詳細はこれから。全国各地のお祭りも
―― 催事の注目ポイントを教えてください。
大﨑 開会式も閉会式も内容はまだまだ検討中です(笑)。これからです(取材は24年11月初旬)。会期中に1万6千人を収容する野外スペースでどんなイベントを作っていくか。もちろん、有名なアーティストのコンサートといった大型イベントは大事なんですが、それだけなら万博でなくてもいい。商業的な縦軸とは異なる、万博でやる意味のある、横幅と奥行きがしっかりある背骨をどうつくるかがポイントです。メディアにもそういう議論があってしかるべきだと思うんですけど、予算オーバーしか取り上げない(笑)。
一般催事では、子どもたちが肌で感じてワクワクして、体験したことが楽しかった思い出になる催し物を考えています。例えば、アジア、中東、アフリカなどそれぞれの国・地域のお祭りで使う太鼓を30個並べて、子どもたちにひとつずつ叩いてもらう。太鼓それぞれに、豊作を祈ったり、魔除けだったり、その地域ごとの叩く意味があります。それを体感して考えることが万博の大きな目的のひとつだと思います。
―― 世界中から観客が訪れます。インバウンド向けに考えていることもありますか。
大﨑 予算が潤沢にあるわけでもなく、特に一般催事は予算ゼロなので苦労していますが(笑)、日本全国各地のお祭りを万博に呼んでいます。それぞれのお祭りは、力のある若者が神輿を担いで、その上では子どもたちが太鼓を叩いたり、笛を吹いたりして、神輿の周囲を熟練の年配者たちがガードしながら歩く。地域の人たちは、地元のお寿司とか季節の地産地消の料理を振る舞う。お祭りは地域社会の共同体の維持装置であり、連綿と続いてきた日本人のライフスタイルがすべて詰まっています。その共同体があるからこそ、社会課題の解決にもみんなで助け合いながら向かっていける。万博に来た世界中の人たちに参加してもらって、地域の人たちと触れ合うことで日本の伝統文化を体験していただきたいです。
―― 今回の万博が、子どもたちや若い世代が担っていく未来へ残すものをどう考えますか。
大﨑 万博は言語を超える共通体験です。世界を知るからこそ、僕らが暮らす日本ってどんな国だろうって考えることにつながります。そこから何かに気付いてほしい。
今の若い世代は、ボランティアなど社会貢献活動に積極的で、ソーシャルマインドがすごく高い。だからこそ、万博で提示された社会課題にしっかり向き合って、神輿を担ぐように力いっぱいチャレンジして、失敗もたくさんしてほしい。そこで学ぶことがあるわけですから。僕ら昭和世代は、彼らの挑戦を影で見守りながらガードする。もし、どうしようもない困難にぶつかったら助ける。彼らがつくっていく新しい日本に僕は期待しています。



