物流や災害現場の捜索など、さまざまな分野で活用が期待されるドローン。日本で最先端を走るのは、歯科医院を営む傍ら趣味が高じて会社を立ち上げたオタク社長だった。エアロジーラボの谷紳一氏に、ドローンビジネスの現状と同社の事業について聞いた。
取材協力者:谷紳一・エアロジーラボ社長
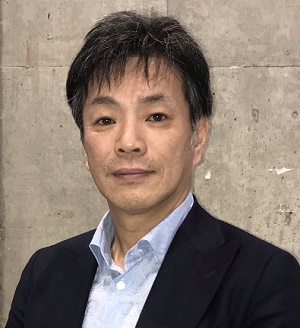 1958年生まれ。大阪大学歯学部卒業後、大学研究室に所属。94年医療法人たに歯科医院を開設。趣味のラジコンヘリコプターによる空中撮影の延長で、ドローンを自作するようになる。12年エアロジーラボを立ち上げ数々のオリジナルドローンを開発。大阪万博に向けた「HyDorone(仮称)」設立準備委員会委員長に就任。
1958年生まれ。大阪大学歯学部卒業後、大学研究室に所属。94年医療法人たに歯科医院を開設。趣味のラジコンヘリコプターによる空中撮影の延長で、ドローンを自作するようになる。12年エアロジーラボを立ち上げ数々のオリジナルドローンを開発。大阪万博に向けた「HyDorone(仮称)」設立準備委員会委員長に就任。ハイブリッドドローンの特徴と長所とは
2016年から毎年開催されている国内最大のドローン関連展示会「ジャパン・ドローン」。2019年は3月13~15日の期間に幕張メッセで行われた。
NTTドコモ、ソフトバンク、日立製作所といった大企業もブースを構える中で、独自性を発揮していたのが大阪に拠点を構えるエアロジーラボだ。
大きな特徴は、動力源にバッテリーではなく燃料に混合ガソリンを用いた「ハイブリッドドローン」で展開していること。谷社長は言う。
「ハイブリッドエンジンのドローンを日本で初めて動かしたのは、おそらくわれわれです。現在も、手掛けているところは他にないと思います」
ドローンの性能の指標として重要なのが、飛行時間とペイロード(搭載可能な重量)だ。ハイブリッドドローンの場合、同じペイロードだと飛行時間はバッテリードローンの約5倍。機体そのものの価格は若干高めとなるが、バッテリー交換費用などが不要なため、年間のランニングコストを100万円以上削減することができる。
「ドローンは垂直方向に上がるための大きなエネルギーが必要で、重さと飛行時間が密接に関係しています。一般的に、カメラを搭載したドローンは15分から20分くらいしか飛べず、産業用に特別に設計した場合でも40分程度が限界です。これでは物流や建造物の検査用途にはほとんど役に立ちません」
実証実験でハイブリッドドローンの優位性を証明
ハイブリッドドローンの優位性が証明されたのが、2018年12月に岡山県和気町で行われた荷物配送の実証実験だ。10キロメートル離れた集落まで、通常は自動車で配送している生活用品などを、河川上空の飛行ルートを使ってドローンで届ける試み。災害時などに、集落が孤立することを想定したものだ。
最大2キログラムの商品を運ぶのに、他社のドローンは飛行時間が約15分、飛行距離が5~7キロメートル程度だった一方、エアロジーラボのハイブリッドドローン「エアロレンジ1型」はルートを2往復、40キロメートル飛行という結果をたたき出した。燃料やバッテリーの残量を見ると、100キロは飛ばせることが確認できたという。
また、最新の「エアロレンジ2型」を使って、無給油、バッテリー交換なしという条件の元でも実験が行われ、ペイロード5キログラムで20キロメートルの飛行に成功した。
「参加した企業の中で、ウチがダントツでした。ハイブリッドドローンのアドバンテージがどれだけあるかが証明された格好です」と、谷社長は語る。
谷社長がハイブリッドドローンを導入した経緯
ハイブリッドドローンの優位性が証明されながらも、まだほとんど導入されていないのはなぜか。その理由について、谷社長はこう話す。
「日本においてドローンはまだ黎明期なので、仮にアイデアがあっても実行する人が少ないんです。また、日本でドローンビジネスを考えている会社は、製品を輸入して運用で儲けようというところがほとんど。われわれのように開発・製造を手掛ける会社が少ないというのも理由です」
谷社長がハイブリッドドローンをつくったのは、もともと中国製のハイブリッドエンジンが出たという話を聞きつけたからだった。
あまり期待はしていなかったものの、実際に機体に積んで飛ばしてみると、ペイロードを懸けなければ飛行時間は3時間にも伸びた。エンジン自体は模型用の簡素なもので、それに発電機(ジェネレーター)を取り付けただけだったが、驚くほど性能が向上したのだ。
とりあえず取り付けた中国製エンジンで成果が出たため、さらに小型、高品質なエンジンを求めて手を組んだのが、世界でも唯一無二のロータリーエンジンがつくれると評判の日東工作所だ。同社のロータリーエンジンは、あのマツダのエンジニアが舌を巻くほどレベルが高く、他で真似できないものだという。
ロータリーエンジンの長所は振動の少なさと、アルコールや水素でも飛ばせるなど、使用できる燃料の幅が広い点にある。
その利点を生かすべく、水素ロータリーエンジンによる有人飛行ドローンの開発プロジェクトの委員長に谷社長は就任。2025年開催の大阪万博で、デモフライトを行うことを目指している。
ラジコン製作から始まった谷社長とドローンとの関わり
谷社長はもともと歯科医師で、エアロジーラボの社長業の傍ら、今でも医院経営を継続している。ドローンと関わるようになったのは、趣味のラジコン操縦の延長からだ。
「一般的に、ラジコンファンは本物に近い機体をつくって飛ばすのを楽しみにしていますが、自分の場合はラジコンを遠隔ロボットとして捉えて、形よりも空からの景色などを見るのが目的だったんです。だから、ラジコングライダーにもヘリにも全てカメラを積んでいました」
撮影の際、谷社長が求めたのはファースト・パーソン・ビュー(一人称視点)。つまり、パイロットがコクピットから見るのと同じように風景を見たかったのだという。
そこで、ラジコンに複数のカメラを積んだが、シャッターを切る瞬間などに操縦の手が離れてしばしば落下してしまうという問題があった。
そんな時に得たのが、欧州でマルチローターヘリコプター(ドローン)がコアなマニアの間で流行っているという情報だった。谷社長はさまざまな関連フォーラムに参加したり、パーツを輸入して自分で組み立てたりするようになった。
その後、日本でもドローンブームが到来し、メディアでも自動航行や自動着陸できるドローンが話題に上るようになったが、谷社長にしてみれば、いずれも自分が以前からやってきたことばかり。特に目新しさも感じなかった。
「日本で自分より進んだことをやっている人はいない」
こう確信したことが、ドローンの会社を起業した理由だ。
「日本にドローンが入ってきたのは5年ほど前ですが、アマチュアながら私は10年前から自作していたので、誰よりも経験が豊富でした」
製品を輸入して運用するだけでなく、機体の設計・開発から組み立てまで手掛け、どんな形式のエンジンでもすぐに積めるようにできるのがエアロジーラボの強みだ。
「もともとマニアだったから、最初からドローンは“自分で作るもの”でした」と谷社長は言う。
エアロジーラボではドローンのシェアサービスや空撮によるコンテンツ事業なども手掛けているが、最も力を入れるのは開発・製造の部分だ。
購入品を運用するだけのビジネスと違い、開発・製造に手を出すのは資金面などのリスクが高い。
しかし、もともとドローンが好きで自腹を切って製作してきた谷社長にはそんなことはお構いなし。だからこそ、国内ドローンの先駆者としてユニークな存在になり得ている。
日本におけるドローンビジネスの可能性
機体、サービスを含めた国内ドローンビジネスの市場規模は、2018年度に860億円、24年度には3711億円になると見込まれている(インプレス社調べ)。だが、日本でドローンビジネスを展開するにあたって、大きな壁が法規制の問題だ。航空法によって飛行可能な区域が非常に制限されており、使用できる電波も限られている。長距離を飛ばそうとすると、目視できる範囲外の飛行も必要になるが、現状では認められていない。
「ドローンを社会実装しようと思えば、目視外飛行ができないと意味がありません。さらに、それを行うためには使える電波も増やさないといけない。本来は携帯電話を搭載して映像を送れば良いのですが、現状では無理です」
法規制の問題がクリアできれば、エンジンやジェネレーターの効率向上など、日本企業が得意な技術面のブラッシュアップで強みを出せる可能性があるとも谷社長は指摘する。
こうした法規制の問題も相まって、今のところドローンビジネスで利益を出している企業は日本にはない。物流一つをとっても、数百円の商品の配送一回に、数万円のコストが掛かるのが現状。通常のビジネスとして成立させるためのハードルは高い。
そんな中、可能性を見出せるのが「プライスレスな分野」だと谷社長は言う。
「買い物難民の救済や災害救助など、コスト度外視で取り組まなければいけない分野から実装が進んでいくと思います。他にも、造船設備や巨大建造物の検査といった、人命がかかわる分野からの引き合いも出てきています」
大量生産でコスト競争を仕掛けるのではなく、高価でも社会的に有益と認められる分野で勝負していく考えだ。
【テクノロジー】の記事一覧はこちら
経済界 電子雑誌版のご購入はこちら!
雑誌の紙面がそのままタブレットやスマートフォンで読める!
電子雑誌版は毎月25日発売です
Amazon Kindleストア
楽天kobo
honto
MAGASTORE
ebookjapan






